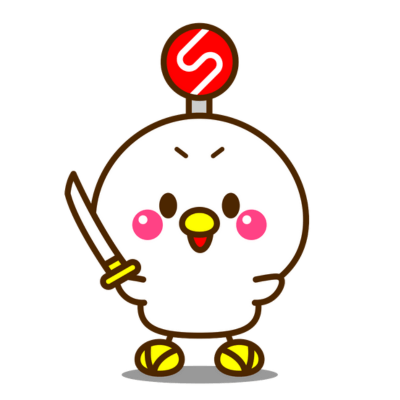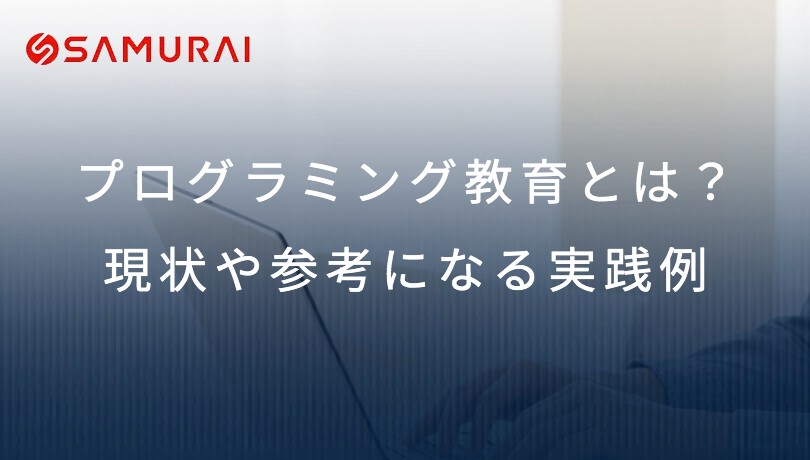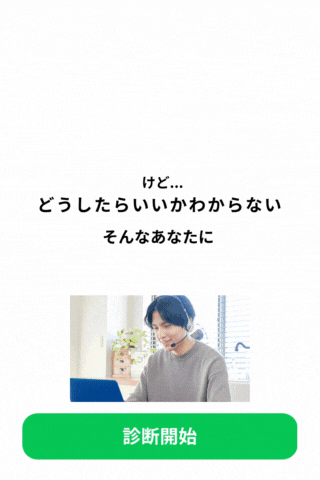プログラミング教育が必修化されて、何か問題点や課題はないのだろうか?
プログラミング教育で実際どんな内容を勉強するのか、教材や実践例を知りたい
プログラミング教育とは、学習指導要領の改訂に伴い、2020年度小学校から中学校、高校と順次必修化されることとなった情報教育のことです。
プログラミング教育が必修化され、現状どのような効果が得られているのか、また問題点や課題はないのか、気になる方もいるのではないでしょうか?
この記事では、プログラミング教育の実践例を紹介し、現状と課題を検証します。またプログラミング教育の今後の展望や、子供たちの将来もお伝えします。
プログラミング教育とは

プログラミング教育とは、平成28年度に改訂された学習指導要領(以下、新学習指導要領)にもとづく情報教育のことです。
学習指導要領とは、全国の学校で一定の水準を保った教育を行えるように文部科学省が定めている基準です。
学習指導要領は、これまでおよそ10年に1度見直しが行われてきました。プログラミング教育も、学習指導要領の改訂に伴い必修化されました。
プログラミング教育の必要性については、次の記事でも解説しています。合わせてご覧ください。
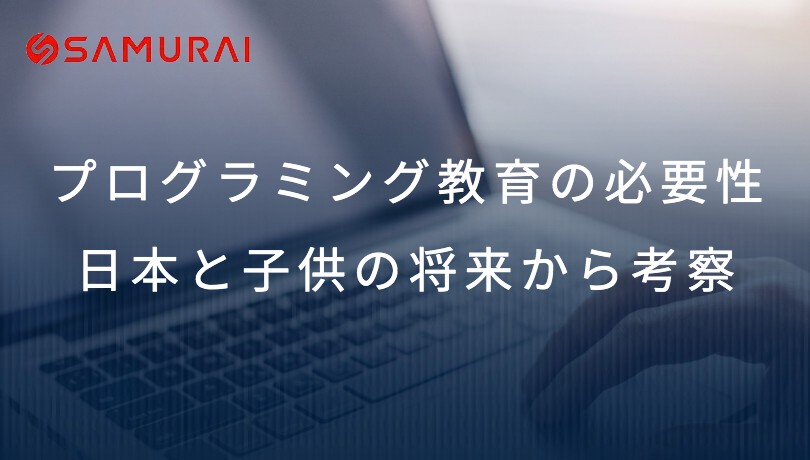
プログラミング教育の内容
プログラミング教育では、コンピュータが動く仕組みや日常生活の中での活用事例などを学びます。
小学校、中学校、高校のプログラミング教育の内容は下記のとおりです。
- 小学校
算数や理科のような既存の教科の中でプログラミング的思考を取り入れた学習を行います。 - 中学校
技術・家庭科(技術分野)「D 情報の技術」の中で、プログラミングや関連技術を学びます。 - 高校
「情報Ⅰ(必修)」と「情報Ⅱ(選択)」の授業でプログラミング教育が行われます。学校によってはプログラミング言語を学習します。
プログラミング教育は、「プログラミング」という教科が新設されるわけではなく既存の教科に組み込む形で行われます。
プログラミング教育の内容について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
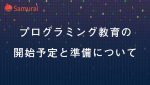
小学校におけるプログラミング教育の種類

小学校のプログラミング教育をわかりやすく分類すると、大きく下記の3種類です。
- 各教科の中で実施するもの
- 教科とは別に授業を行うもの
- 特定の児童を対象にしたもの
それぞれの内容を解説します。
各教科の中で実施するもの
プログラミング教育は下記の教科で実施されます。各教科の中で実施するもののうち、新学習指導要領に例示されているのは下記の教科です。
- 算数
- 理科
- 総合的な学習の時間「情報化の進展と生活や社会の変化」
- 総合的な学習の時間「まちの魅力と情報技術」
- 総合的な学習の時間「情報技術を生かした生産や人の手によるものづくり」
たとえば「算数」では、「正多角形を描くプログラミングを行う」という授業をとおして、正多角形の特徴やプログラミングで正確な描画ができることなどを学びます。
プログラミング教育はほかにも、下記の教科で実施されます。
- 音楽
- 社会
- 家庭
- 総合的な学習の時間(プレゼンテーション)
- 国語
- 図画工作
教科とは別に授業を行うもの

「教科とは別に授業を行うもの」とは、プログラミングの体験授業などを実施するケースです。
企業と提携した授業や、プログラミングで自分の描いた絵を動かす授業など、楽しく学べるカリキュラムがあります。
特定の児童を対象にしたもの
「特定の児童を対象にしたもの」とは、クラブ活動など、一部の生徒を対象に行われるプログラミングの授業です。プログラミングの詳しい知識を身につけた児童は、普段の授業でクラスメイトをフォローできます。
プログラミング教育の授業内容について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
プログラミング教育必修化の背景

プログラミング教育が必修化されることになった背景には、急速な社会の変化があります。特に、近年のインターネットやAIといった情報技術の進化は目覚ましいものがあります。
今後、社会や人々の生活はさらに大きく変わっていくと予想されるでしょう。
これらの技術革新は、人々の生活を豊かで便利にするために行われています。しかし、技術の進歩が下記のような新たな不安を生んでいることも事実です。
- 時代の変化で、今の学校教育が通用しなくなるかもしれない
- 将来、AIに人間の仕事が奪われてしまうのではないか
- IT技術の進化が加速していく中で、IT人材が不足する可能性がある
プログラミング教育は、このような不安や課題を解決するために必修化されました。
子供たちは、プログラミング教育でIT技術の使い方を覚えるだけでなく、「なぜこんなことができるのか」「この技術が生まれたのは何故なのか」といった仕組みや背景を考え、“気づき”を得ます。
主体的にIT技術と向き合い、みずから考えて設計していく経験を積むことは、多様な社会変化に対応できるスキルを持った人材の育成につながっていくでしょう。これは、社会にとっても子供たちにとっても有益なことです。
文部科学省も、「プログラミング教育によってコンピュータの仕組みや活用法を理解することは、これからの社会を生きる子供たちの可能性を広げることにつながる」という見解を示しています。
プログラミング教育が必修化された背景について、下記の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
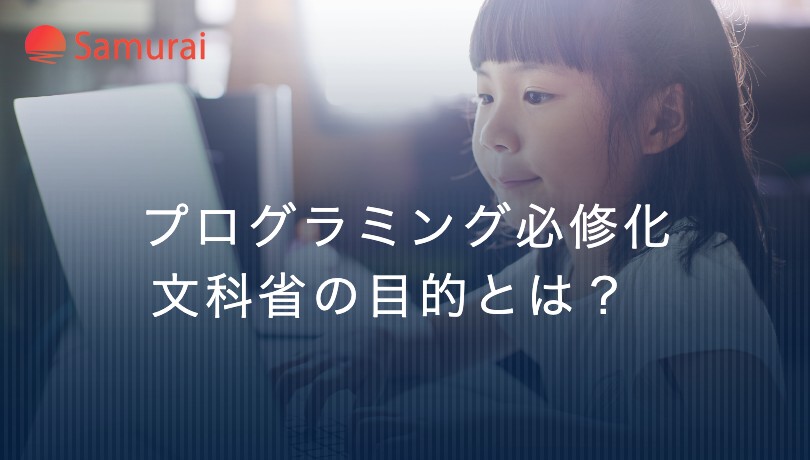
小中高プログラミング教育の目的

小学校、中学校、高校、それぞれのプログラミング教育の目的をまとめました。
小学校・中学校・高校、それぞれ見ていきましょう。
小学校のプログラミング教育
2020年に必修化された、小学校のプログラミング教育の目的(概要)は、主に下記の3つです。
- 論理的思考力を育てる
- 身の回りにある便利な道具にプログラミングが活用されていることに気づく
- 各教科での学びをより確実なものにする
プログラミングにつながる考え方を身につけたり、プログラミングでいろいろな課題を解決できることを知ったりすることが主な学習内容になります。
小学校のプログラミング教育の目的や内容、必修化の背景について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
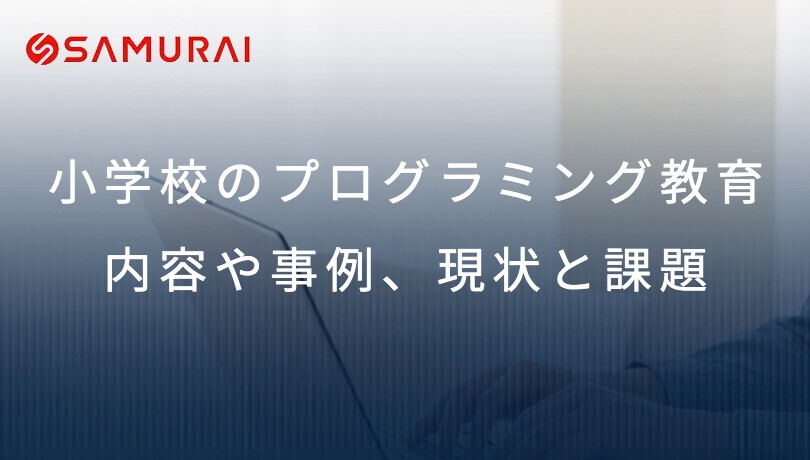
中学校のプログラミング教育

中学校のプログラミング教育の目的(概要)は、プログラミングの基礎を身につけることです。
中学校では、以前から「プログラムによる計測・制御」といったプログラミング教育に通ずる授業が取り入れられていました。これが拡充され、2021年から全面実施されます。
新たに加わった学習内容は「双方向性のあるコンテンツによる問題解決」や「計測・制御システムの構想」などです。これまでは、「ソフトをどう使うか」と言った受動的な活用法を学んでいたのに対し、これからは「プログラミングやネットワークを能動的に活用して課題を解決する」ことを学びます。
プログラミング教育とSociety5.0
中学校のプログラミング教育必修化の背景には、「Society5.0」があります。「Society5.0」とは国が目指す「仮想空間と現実空間の高度な融合によって、経済発展と社会的課題の解決を行う人間中心の社会」を指します。
中学校のプログラミング教育必修化により、将来、課題解決力を有した人材が社会に輩出されることが期待されています。
中学校のプログラミング教育について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
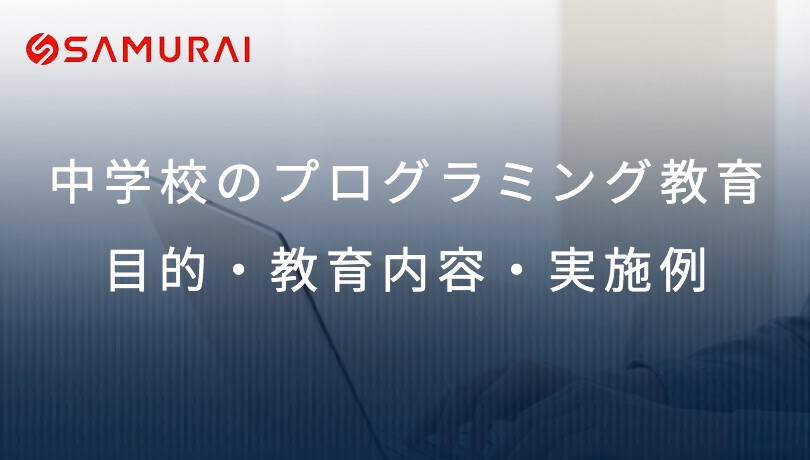
高校のプログラミング教育
高校のプログラミング教育の目的は、将来役立つような、プログラミングの実践的なスキルを身につけることです。
小学校と中学校のプログラミング教育は、「全面実施」です。一方高校のプログラミング教育は、2022年度から年次進行で実施されます。
2022年に1年生として高校に入学する生徒から順次、新学習指導要領に即したプログラミング教育を受けることになります。
高校では、これまでも「情報」の中の「情報の科学」という授業でプログラミングに関する教育が行われてきました。ただし情報科学は選択科目なので、全員が履修するわけではありません。
実際に、「情報の科学」を選択してプログラミング教育を学ぶのは、全体の2割程度だそうです。
「情報Ⅰ」では、情報技術を活用した問題解決や、ネットワーク、データベースの基礎知識などを学びます。また、選択科目の「情報Ⅱ」では、より発展的な内容を学びます。
高校のプログラミング教育について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
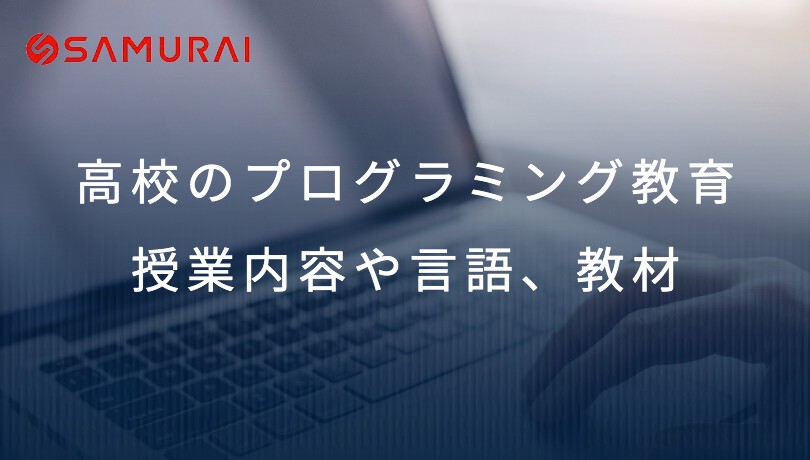
プログラミング教育のメリット

プログラミング教育を受ける子供たちにとってのメリットは、主に下記の3つです。
- 早期にコンピュータに親しむことができる
- 将来の選択肢が増える
- プログラミング以外の学習の効率を上げる
ひとつずつ見ていきましょう。
早期にコンピュータに親しむことができる
プログラミング教育必修化によって、すべての児童が早期にコンピューターに親しめるようになることはメリットです。
なかには、子供が小さいうちからタブレットを持たせたり、プログラミング教室に通わせたりしている家庭もあるでしょう。しかし、すべての子供がこのような環境にいるわけではありません。
プログラミング教育必修化によって、情報化社会で育つ子供たちが等しくコンピューターを始めとしたIT技術と接する機会を持てるのです。
将来の選択肢が増える

プログラミング教育により、将来の選択肢が増えることも子供にとってのメリットです。
プログラミング教育で磨かれる論理的思考力や課題解決力は、将来ほとんどの職業で活用できる能力です。
プログラミング教育を受けることで、子供はさまざまな職種で活躍できる可能性が高くなります。
プログラミング以外の教科における理解が深まる
次のメリットとして、プログラミング教育をとおしてほかの教科の理解が深まる、ということが挙げられます。
プログラミングを従来の教科に組み込むことで、一つひとつの手順を確認したり、仕組みを考えたりします。例えば、算数でプログラミングを使って正多角形をかくとき、図形の性質をよく考ることで答えが導き出せるようになっています。
プログラミング教育で使われる教材

プログラミング教育の現場では、さまざまな教材が使われています。それぞれの授業に適した教材を選ぶために、教材ごとの特徴とメリットを掴んでおきましょう。
プログラミング教育で人気の教材は、下記の5つです。
- Scratch(スクラッチ)
- Viscuit(ビスケット)
- プログル
- プログラミングカード
- 文部科学省が推奨する教材
教材の特徴を、一つひとつ、見ていきましょう。
Scratch(スクラッチ)

Scratchは、マサチューセッツ工科大学が開発したビジュアルプログラミングです。Scratchは、小・中学校での活用事例や高校の「情報Ⅰ」の教科書への掲載実績があります。
ブロックを組み合わせるだけでプログラミングができるので、子供でも簡単に扱えるでしょう。
特に小学校のプログラミング教育での活用事例は豊富で、「Scratchを使って正多角形を描く」「リズムを作る」といった多くの授業で利用されています。
プログラミング教育で使われる優良教材、Scratchについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
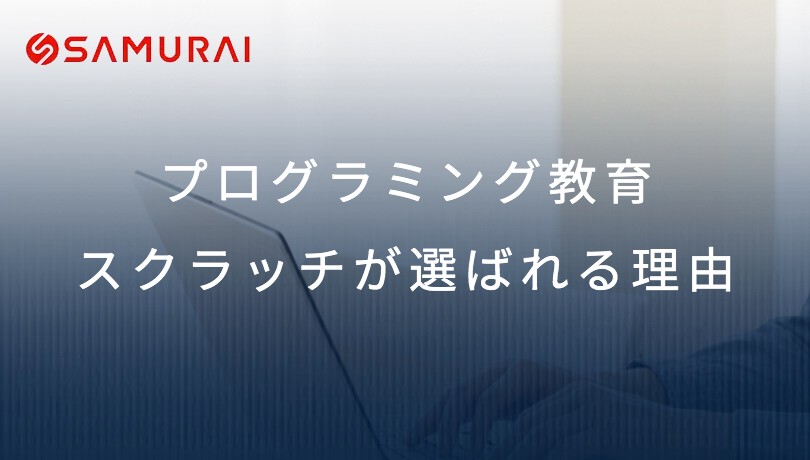
Viscuit(ビスケット)
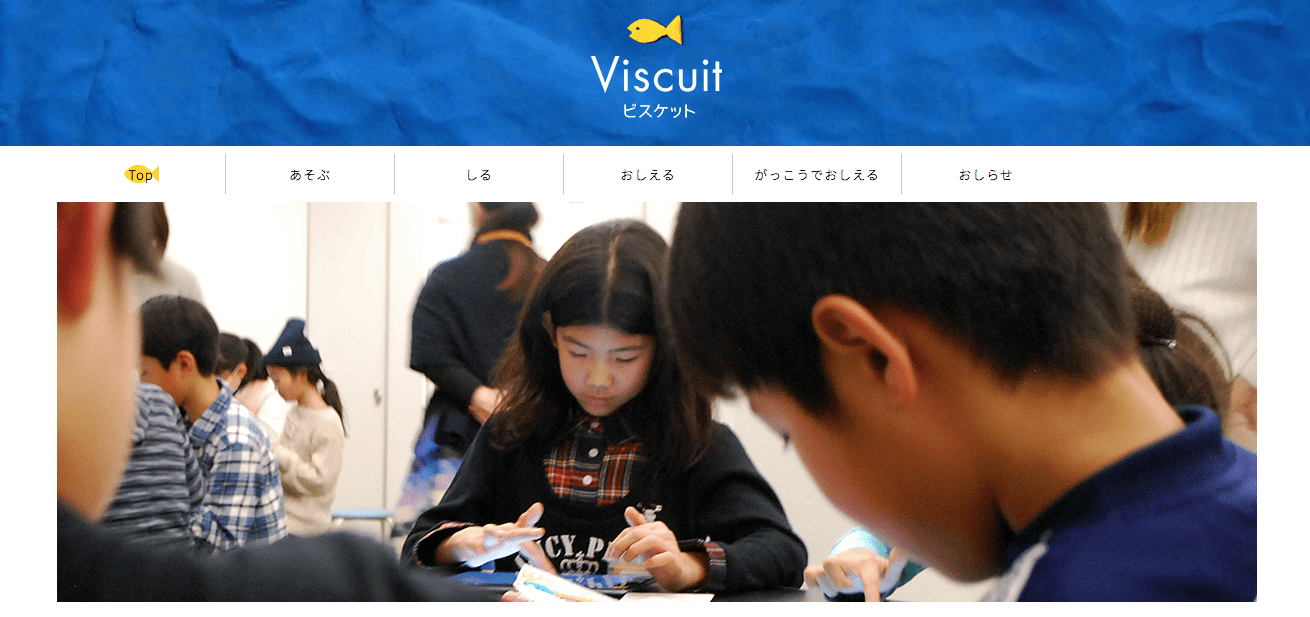
Viscuitも、Scratchと同じビジュアルプログラミングです。メガネと呼ばれる円の中にイラストを配置することでプログラミングを行います。
Viscuitは、「そもそもコンピュータとはどういうものなのか」「何ができるのか」を直感的につかめるように作られています。
例えば、キャラクターを一歩前へ進めるプログラミングを行いたい場合、Scratchでは「1歩動かす」というカードを使いますが、Viscuitでは左右のメガネに移動前のキャラクターと移動後のキャラクターの絵をそれぞれ置きます。活用事例としては、「好きな色の花火をあげる」「魚を泳がせる」などがあります。
プログル
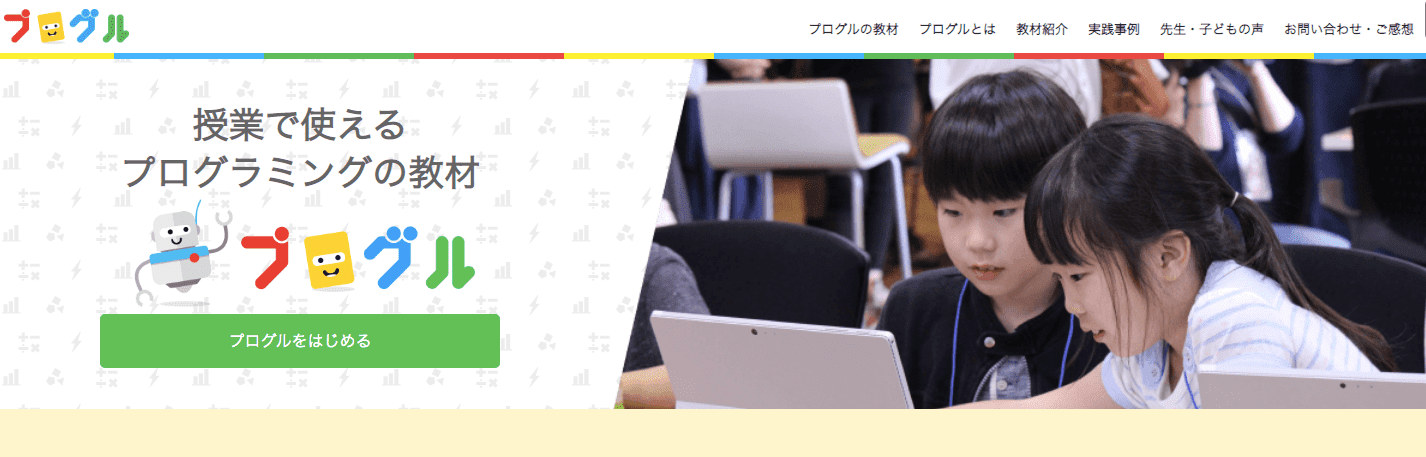
プログルは、小学生向けのプログラミング教材です。「課題をクリアすることでステージを進めていく」という内容で、ゲームのように楽しみながらプログラミングを学べます。
指導案や授業実施例の動画なども用意されているので、プログラミング教育に不安がある教員でも安心です。
なおプログルシリーズには、中学生向けの「プログル技術」、高校生向けの「プログル情報」もあります。
プログラミングカード
カードを使って疑似プログラミングを行うのが、「プログラミングカード」での学習です。
リズムカードや車の動き方を指示するカードなどを組み合わせることで、音楽やドライブコースの疑似的なプログラミングができます。パソコンやタブレットを使わないので、小学校低学年の子供のプログラミング入門にも適しているでしょう。
カードで作ったプログラミングは、Scratchで実行することも可能です。また、カードを読み込むことで、指定通りに車を走らせることができる教材もあります。
文部科学省が公表する研修教材
文部科学省は、教員用の研修教材を公表しています。
文部科学省の「小学校プログラミング教育に関する研修教材」では、プログラミング教育の概要やScratchやViscuitなどを使った実際の指導例などが紹介されています。
テキストだけでなく、動画教材もあるので、授業の参考にできます。また、子供に具体的な操作方法を教えるときに役立つでしょう。
プログラミング教育に適した教材について、下記の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

プログラミング教育に適したツールについては、下記の記事でも紹介しています。合わせてご覧ください。
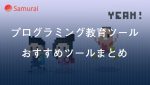
プログラミング教育の現状

小学校では、プログラミング教育が必修化されてすでに1年半以上が経過しています。
続いて、プログラミング教育の実践例やプログラミング教育によって起こった変化について見てみましょう。
プログラミング教育の現状について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
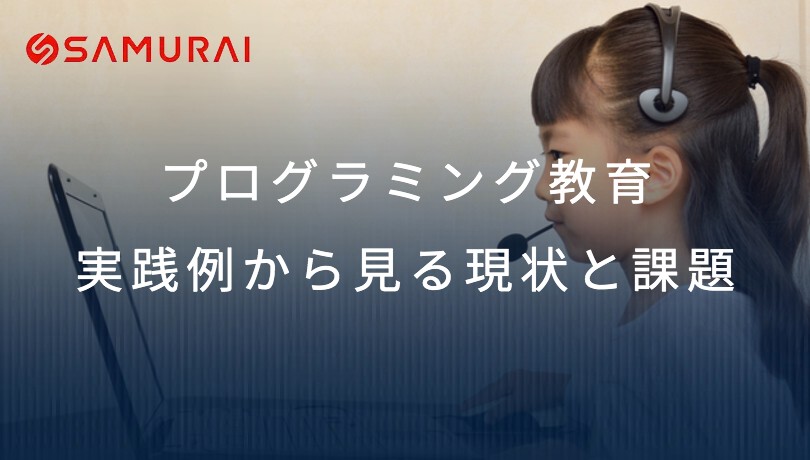
プログラミング教育の実践例
実際に小学校で行われたプログラミング教育の実践例を2例、ご紹介します。
- 1. 私たちの生活を豊かにする未来の宅配便(総合的な学習の時間)
小学校5年生の実践例です。宅配便の仕組みを学んだ上で、未来の宅配便について考えました。併せて、仮想の町の宅配車を意図した通りに走らせるプログラミングも行っています。
- 2. くりかえしをつかってリズムをつくろう(音楽)
小学校2年生が、ビジュアルプログラミング「Scratch」を使ってリズムを作りました。拍子やリズムに関する授業を行った後、カードを使ってリズムを考え、Scratchで再生します。実際に音を聞いた後は、さらに面白い音楽になるように工夫してグループ発表も行いました。
プログラミング教育の影響

プログラミング教育が始まったことで、子供や学校の「当たり前」にさまざまな変化が起こっています。
- 子供にとって、パソコンやタブレットが身近なものになった
- 小学校によってはパソコンの貸し出しを行っているところもある
- 小学校向けのプログラミングスクールや、子供向けのプログラミング教材が増加した
プログラミング教育によって、子供にとってIT機器が日常のものになりました。学校によっては、パソコンなどの貸し出しも行われています。さらに、学校内外で利用できる学習教材や学外のプログラミングスクールなど、子供がプログラミングを学べる環境が充実してきています。
今後、プログラミング教育は学校に留まらず、地域活動へと発展する見込みです。
プログラミング教育の現状について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
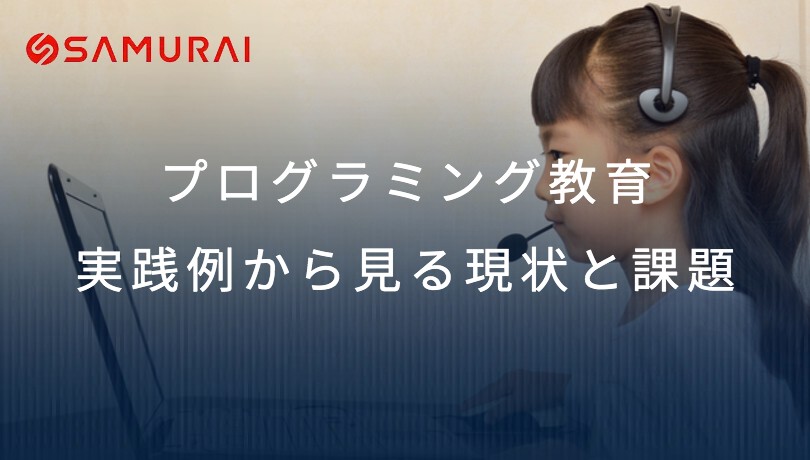
プログラミング教育の課題

プログラミング教育には、展望とともに課題もあります。
プログラミングの現状の課題は、主に下記の4つです。
- 学習環境の整備不足
- セキュリティ対策が必要
- 教員のスキル不足
- 定まったカリキュラムがない
今後のプログラミング教育をより充実したものにしていくために、改善すべき点について解説します。
プログラミング教育の課題や解決法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
学習環境の整備不足

プログラミング教育の最初の課題は、学習環境の整備不足です。
文部科学省の「GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境整備の進捗状況について」の結果から、公立小中学校の端末とネットワーク環境の整備状況を見てみましょう。
- 端末の問題
2021年3月末日時点での端末普及調査では、回答した自治体のうち97.6%が「2020年度中に納入を完了する見込み」と答えています。
なお「納入」とは、「端末が生徒の手元に渡って学校で使えるようになる状態」を指します。多くの学校では端末の整備ができていることになりますが、残念ながら100%ではありません。
- ネットワーク環境の問題
ネットワーク環境の構築を行っている学校のうち、2021年4月から実際にネットワークを利用できると答えた学校は、全体の97.9%でした。
こちらも高い割合で整備が完了しているものの、100%には到達していません。なお、左記の割合に「整備しない」と答えた学校は含まれません。整備しない理由には、統廃合予定であることや小規模校であることなどが挙げられています。
学習環境の整備に関する問題を解決するためには、「何が必要なのか」を明確にしなければいけません。学校の授業に適したスペックや機器類、環境について検討を行い、整備を進めていく必要があるでしょう。
なおプログラミング教育は、パソコンやタブレットを使わずにカードなどを用いて行うこともあります。パソコンやタブレットがないと絶対にプログラミング教育ができないというわけではありません。
各学校が無理なく、子供の可能性を広げるプログラミング教育を行えるよう、視野を広げて方法を考えることが大切です。
セキュリティ対策が必要
プログラミング教育はセキュリティ対策が必要、という点も課題です。
パソコンやタブレットには、生徒の学習の記録が残ります。このような個人情報をどう管理するのか、適切な規定を作らなければいけません。
また、USB機器の使用やインターネットの使用に関しても、十分なセキュリティ対策やリスク管理が求められます。
教員のスキル不足

プログラミング教育は、教員のスキル不足も課題となっています。
各自治体の研修センターでは、教員向けのプログラミング教育ガイドを作成したり、研修会を実施したりしています。こういった研修や、文部科学省が公開している研修教材などを活用して、教員の育成を進めましょう。
定まった学習カリキュラムがない

定まった学習カリキュラムがないことも、プログラミング教育の課題といえます。
プログラミング教育は「1年生の4月に〇〇の内容を勉強する」といった規定に沿って進められているわけではありません。各学校や教員が、それぞれの判断でカリキュラムを設定するため迷うこともあります。
プログラミング教育のカリキュラムで迷ったら
プログラミング教育のカリキュラムを組むときに困難を感じたら、ほかの学校の実践事例集や文部科学省の指導案を参考にするのがおすすめです。
事例や指導案を参考に、適切な指導の進め方を検討しましょう。
【小学校】
文部科学省が、プログラミング教育の実施事例や指導案集を公開しています。
【中学校】
中学校のプログラミング教育についても、文部科学省が実践事例を公開しています。また、各自治体による指導案も公開されています。
- 実践事例:中学校技術・家庭科(技術分野)内容「D 情報の技術」:文部科学省
- 和歌山県教育委員会指導案:きのくにICT教育 中学校プログラミング教育 学習指導案
- 兵庫県・中学校プログラミング教育推進ページ:中学校技術・家庭科(技術分野)プログラミング教育
【高校】
- 実践事例:高等学校「情報」実践事例集:文部科学省
- 河合塾による授業事例:「情報Ⅰ」学習指導要領項目別の事例一覧
- 高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材(演習例を掲載):高等学校「情報」実践事例集:文部科学省
プログラミング教育の問題点について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
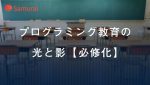
まとめ
「プログラミング教育」は、始まったばかりです。教員や親にとっても馴染みがないものですから、「子供にどんなメリットがあるのかわからない」「適切な指導法がわからない」と不安に感じる人もいるかもしれません。
しかしプログラミング教育の根底にあるものは、難しいコードやプログラミング言語の習得ではありません。「理論的な思考力を養い、子供の将来の可能性を広げる」ことです。
なんのためにプログラミング教育を行うのか、目的を見失わずに子供たちを導いていきましょう。
なお、初心者が知っておくべきプログラミングの基礎知識については、次の記事で詳しく紹介しています。合わせてご覧ください。
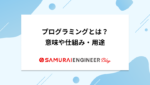
この記事のおさらい
プログラミング教育は、小学校が2020年、中学校が2021年からそれぞれ全面実施、高校は2022年入学の生徒から年次進行でスタートします。
プログラミング教育では、身近な技術におけるプログラミングの活用法やプログラミングによる課題解決、論理的な思考方法などについて学びます。