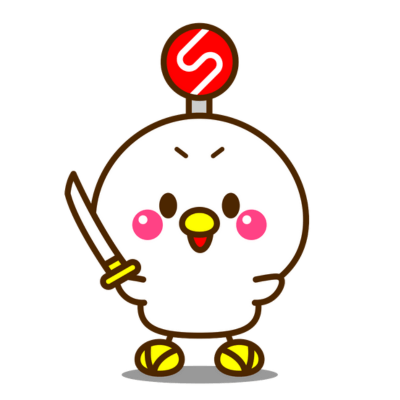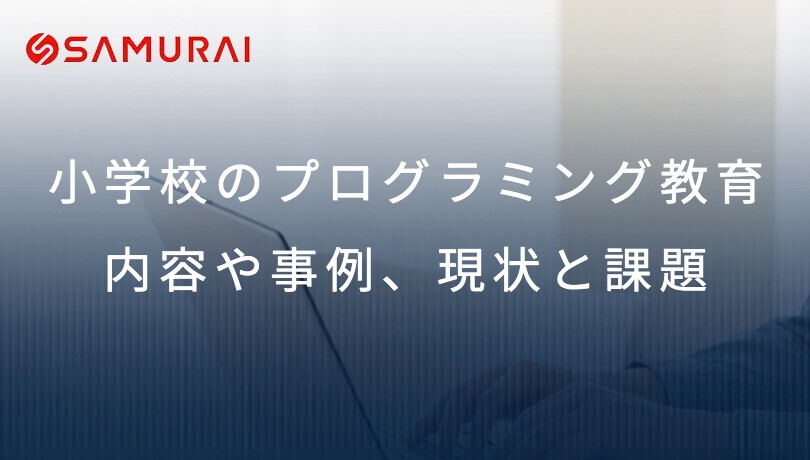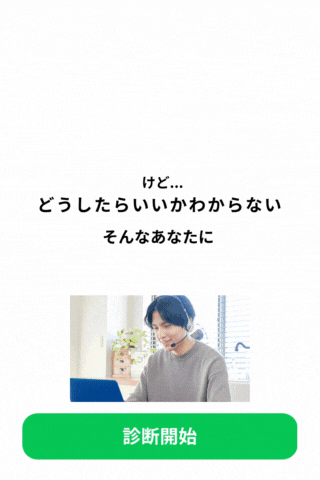2020年、小学校のプログラミング教育が必修化されました。始まったばかりの制度なので、指導計画の立て方や、授業展開に悩む先生も多いです。
この記事では、指導計画を立てるときのヒントや、参考にしたい授業の事例を紹介します。
プログラミング教育必修化の背景や本来の目的についても解説しますので、改めて確認し子供に適切な学びを与えましょう。
プログラミング教育について、下記の記事で詳しく、わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
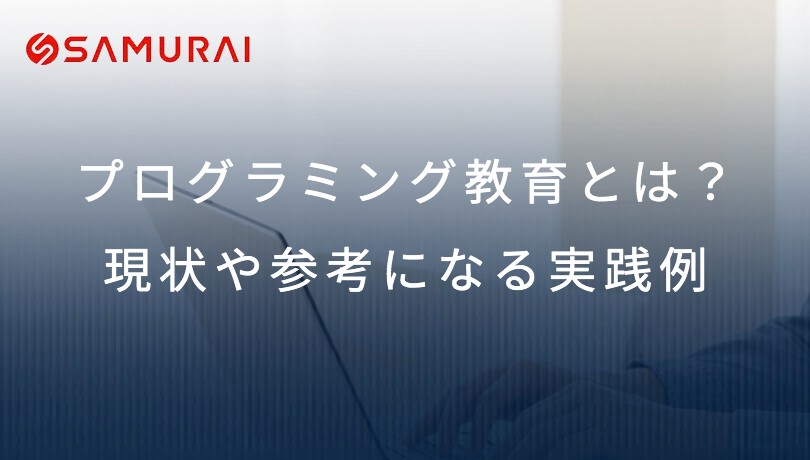
小学校のプログラミング教育必修化の背景

文部科学省が提示するプログラミング教育のねらいは、下記の2つです。
- IT人材の確保
- 子供が社会の変化に対応できるようにする
それぞれ、詳しく解説します。
参考:総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室「子供向けプログラミング教育の現状に関する調査研究の請負成果報告書」
プログラミング教育必修化の背景について、詳しくは下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
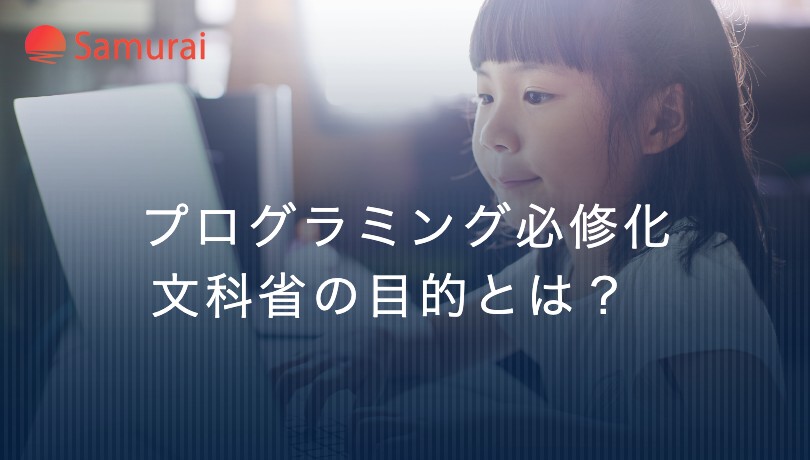
IT人材を確保する
小学校でプログラミング教育が必修化された背景には、IT人材不足があります。
子供のうちからITに触れる機会を設けることで、将来を担うIT人材を輩出するのがプログラミング教育のねらいです。
プログラミング教育により、日本の産業競争力を強化されることが期待されています。
子供が社会の変化に対応できるようにする

小学生のうちにプログラミング教育を受けることで、将来社会の変化に対応できるようにすることも、必修化のねらいです。
IoTやAI、ロボットといった技術が広がるなかで、急速な社会の変化が起こっています。こうした変化は、今後も続いていくと予想されます。
小学生はプログラミング教育で、将来の変化にも対応できるスキルを習得できます。
小学校の新学習指導要領とプログラミング教育の内容

小学校でプログラミング教育が必修化され、1年が経過しました。しかし具体的にどのようなことが行われているのか、わからない方もいるでしょう。
続いて、小学校の新学習指導要領とプログラミング教育の授業内容について、解説します。
小学校の新学習指導要領

新学習指導要領に記載された小学校のプログラミング教育の目的を要約すると、 下記のとおりです。
- 小学生がコンピューターに慣れる
- ITを活用するための論理的思考力を身につける
それぞれ詳しく解説します。
小学校プログラミング教育の授業内容
小学校のプログラミング授業で、コードを書いたりプログラミング言語の学習をしたりすることはありません。
新学習指導要領で例示されるプログラミング教育の内容は、下記のとおりです。
- 算数:プログラミングを使って図形を正確に作図する
- 理科:プログラミングで機械を動かす
- 総合的な学習の時間
各教科の授業内容を、具体的に見ていきましょう。
算数
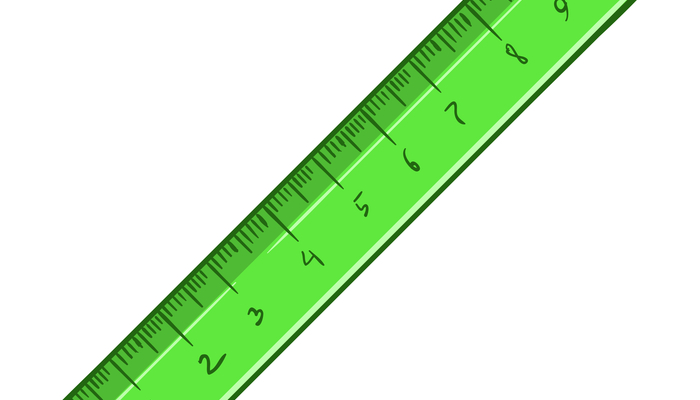
5年生の算数では、プログラミングで正多角形の作図を行う授業が例示されています。
具体的には、プログラミングで「正確に繰り返し作図する」「一部を改変していろいろな正多角形の描画に応用する」といった内容です。
理科
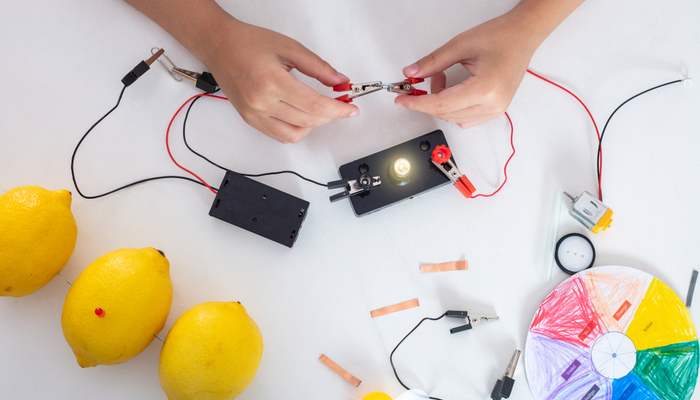
6年生の理科では、プログラミングを使って電気で動く道具を活用する授業が例示されています。具体的には、「機械に条件を与えて意図したとおりに動かす」「条件を変えることで動きを変える」といった内容です。
例えば「スイッチを押せば3秒間電気がつく」というプログラムを組んで、実際に動かしてみる授業が想定されます。
総合的な学習の時間
探求的な学習を行う一貫として、「情報収集と発信」や「情報が日常生活や社会に与える影響」を学びます。
プログラミングが普段の生活とどのように結びついているのか、確認します。
その他

文部科学省が公表した「小学校プログラミング教育の手引き」によると、プログラミングは下記の授業でも行われます。
- 音楽
- 社会
- 家庭科の授業
- 課外活動
プログラミングは、さまざまな形で小学校の授業に組み込めます。どのように活かしていくか各学校、人員や設備も含め検討する必要があります。
小学校プログラミング教育の指導計画を立てるときのヒント

プログラミング教育では、「プログラミング」という独立した授業が追加されるわけではありません。そのため「どこから始めれば良いか迷ってしまう」という教師もいるのではないでしょうか。
そこで、指導計画を立てるときのヒントとなる資料を3つ紹介します。
<小学校プログラミング教育指導計画のヒントになる資料>
- 文部科学省「小学校プログラミング教育指導案集」
- 株式会社教育ネットの「プログラミング教育年間指導計画案」
- 各自治体の教育委員会「年間指導計画例」
それぞれの内容を詳しく解説します。
文部科学省「小学校プログラミング教育指導案集」
「小学校プログラミング教育指導案集」は文部科学省が公開する、「みらプロ」という民間企業との提携を前提としたプログラミング教育の指導案です。
「総合的な学習の時間」における、プログラミングの取り入れ方について解説されています。
なお、みらプロの取り組み自体はすでに終了しているため、指導案と同じ授業はできない可能性があります。しかし、プログラミングが社会でどう活用されているかといった内容も説明されているので、指導計画の基礎知識として役立てても良いです。
参考:令和元年度 小学校プログラミング教育指導案集:文部科学省
株式会社教育ネットの「プログラミング教育年間指導計画案」
情報モラルやプログラミング教育の支援を行っている株式会社教育ネットでは、「プログラミング教育年間カリキュラム表」を無料で提供しています。
パソコンやタブレットを使わずにプログラミングの考え方を学ぶ「アンプラグド・プログラミング」と、パソコンなどを使ったプログラミングを組み合わせて学ぶ内容となっています。
各自治体の教育委員会「年間指導計画例」

各自治体の教育委員会の中には、プログラミング教育を含む情報教育の年間指導計画例を公開しているところがあります。
例えば、大分県教育委員会は「情報教育(プログラミングを含む)全体計画例」と「年間指導計画例」を公開しています。
具体的な年間のカリキュラムが低学年・中学年・高学年別に例示されていて、わかりやすい計画例です。ほかの自治体に住んでいる人も見ることができますから、参考にしてみてください。
情報教育(プログラミングを含む)全体計画例・年間指導計画例の公開について
小学校プログラミング教育の実践例

次に、実際に小学校で行われたプログラミング教育の例を3つ紹介します。
- 【小学校2年生】算数 しきつめもよう
- 【小学校3年生】デジタル水族館をつくろう!
- 【小学校5年生】偶数と奇数を判別する方法を考えよう
ほかの学校ではどんな授業が行われているのかを知り、カリキュラム作りに活かしましょう。
【小学校2年生】算数 しきつめもよう
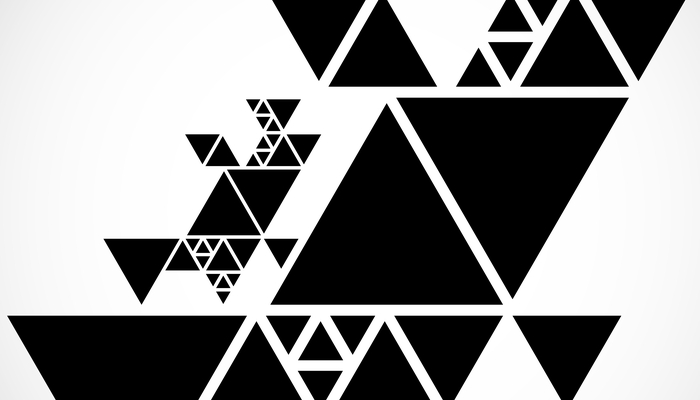
小学校2年生、算数「しきつめもよう」の授業では、折り紙で折った直角三角形や正方形をしきつめて模様を作ります。その後、絵の位置を変化させて魚を動かす「Viscuit(ビスケット)」を使い、プログラミングでしきつめ模様を作成します。
折り紙で模様を作った後「もっと作りたい?」と聞いたり、「いくつのプログラムがあれば模様が作れると思う?」と質問したりして、子供たちが自発的に学ぶ環境づくりができるのです。
参考:小学校プログラミング教育の実施レポート 学習活動名 算数 しきつめもよう 学年 小学校第2学
【小学校3年生】デジタル水族館をつくろう!

小学校3年生の「デジタル水族館をつくろう!」という授業では、前述のViscuit(ビスケット)を使って、自分で描いた海の生き物を動かす、というプログラミングを体験しました。
クラスメイトの作品の良いところや改善点を伝え合うことで、プログラミングの楽しさや活用法を学べます。
3年生が1,2年生に作り方を教える、といった学年を横断した取り組みも行われ、生徒からは「楽しかった」「次は動物園を作りたい」といった感想が寄せられています。
参考:東京都荒川区立尾久西小学校(デジタル水族館をつくろう!)
【小学校5年生】偶数と奇数を判別する方法を考えよう
小学校5年生の「偶数と奇数を判別する方法を考えよう」という授業では、ブロックを組み合わせてプログラムを作るScratch(スクラッチ)という教材を使って、偶数と奇数を判別するプログラムを組みました。
学習の目的は、期待通りの答えを導き出す「条件分岐」の考え方を学ぶことです。フローチャートを使ったり、身の回りの条件分岐を使った仕組みを考えたりして、学びを深めました。
プログラミング教育の内容や実践例について、下記の記事で詳しく解説しています。
小学校プログラミング教育の現状と課題

小学校のプログラミング教育には、今後解決していかなければいけない課題もあります。
- ICT環境の整備
- 指導内容の属人化
プログラミング教育を今後も継続し、効果を上げていくためには、環境の整備と勉強を教える側のフォローが必須です。
課題の内容を詳しく見ていきましょう。
ICT環境の整備が不足する

小学校のプログラミング教育の課題として、ICT環境の整備不足が挙げられます。
プログラミング教育の中には、タブレットやパソコン、インターネット環境が必要なものも少なくありません。
このような機器類やインターネット環境の整備をどのように行うのか、各学校が考える必要があります。同時に、セキュリティや個人情報保護に関する整備も不可欠です。
指導内容に差が生じる
内容に差が生じるという点も、小学校のプログラミング教育の課題です。
普段の授業の中にどのようにプログラミング教育を取り入れていくのかは、「小学校プログラミング教育の手引き」で紹介されています。しかし統一された教材がないので、実際の学習内容や取り組みは学校によってさまざまです。
地域や学校によって子供が受けられる教育に差がでないよう、具体的な指導内容の策定や教員の育成が必要です。
プログラミング教育の問題点について、詳しくは下記の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
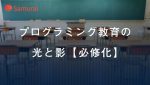
小学校以外でプログラミングを勉強するには?

プログラミングを勉強できる場は学校だけではありません。学校でプログラミングに触れた子供が「面白い!」と感じられたら、さらなる学習機会を与えてあげましょう。
小学校以外でプログラミングを勉強する方法は、下記の2つです。
- 自宅で学ぶ
- スクールで学ぶ
それぞれ、見ていきましょう。
自宅で学ぶ
今、小学生向けのプログラミング教材は豊富なので、自宅で学ぶのもおすすめです。
自宅で行うプログラミング学習には送り迎えの必要がなく、コストを抑えられるというメリットがあります。
無料で利用できるプログラミング学習用動画や子供向け学習アプリなどもたくさんあるので、ぜひ活用してください。ゲーム感覚でできるアプリが多いので、楽しく学べます。
プログラミング学習におすすめの教材については、下記の記事で詳しく解説しています。
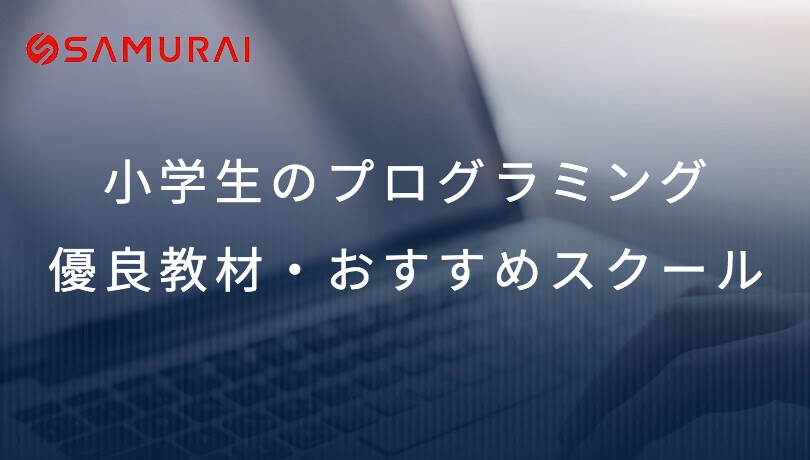
スクールで学ぶ

本格的にプログラミングを勉強するなら、スクールに通うのがおすすめです。
子供向けのプログラミングスクールなら、高いスキルを持った講師に教わることができます。また、子供の興味や集中力を高めやすいカリキュラムが用意されている点も魅力です。
子供向けのプログラミングは、遊びを交えながら学習できます。勉強にあまり興味がない子供や、集中力が途切れがちな子供でも取り組みやすいでしょう。
まとめ

小学校のプログラミング教育は、まだ始まったばかりです。授業展開や指導計画の策定が、うまくいかない場合も考えられます。
文部科学省や各自治体の教育委員会、民間企業などが提供している指導案を参考に検討してみてください。
授業への取り入れ方に迷ったときは、ほかの学校の実践例を参考にするのもおすすめです。「従来の教科の理解度を深める」「情報化社会に対応できるスキルを身につける」といった本来の目的を忘れずに、子供たちの知的好奇心やワクワク感を引き出せる授業を目指しましょう。
また、学校でのプログラミング教育を通じて子供が興味を示したら、自宅やスクールでプログラミングにふれる機会を作ってあげてください。
この記事のおさらい
小学校のプログラミング教育では、論理的思考力を身につけ、身の回りの技術にプログラミングが活用されていることへの「気づき」を重視した学習が行われます。プログラミング言語を覚えるわけではありません。
小学校のプログラミング教育は、主に従来の教科内で行われます。年間のカリキュラムは、文部科学省の教育指導案集や各自治体の教育委員会の年間指導計画例などを参考に立てましょう。