この記事では、活用事例も交え、AWSでできることを解説します。
近年注目が集まっているクラウドの中でシェアが高いAWSについて、基本的な知識を習得したいと考えている人は多いはずです。
AWSは、Amazonが提供するクラウドサービスの総称です。
この記事ではAWSでできることを中心に、AWSの活用事例や面白い使い方も紹介しているのでぜひ参考にしてください。
- AWSを利用すれば、Webサイト・Webサービスの構築・運用が可能
- AWSはシャープ株式会社や任天堂株式会社など大手企業も導入している
- AWSを使うメリットには「費用」、「高機能」、「スピードの向上」が挙げられる
「独学と並行しながら、転職活動できるかな…」
そんな不安を抱えている人は、ぜひ「侍エンジニア」をお試しください。
侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポート。就業活動もIT企業で人事経験のあるキャリアアドバイザーから支援が受けられます。
これまで4万5,000名以上の受講生を指導し「転職成功率99%」の実績を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくAWSエンジニアへの転職が実現できますよ。
Amazon AWSとは?

AWS(Amazon Web Services)について調べていると、
難しい言葉が並んでいてよくわからなかった…
知りたい情報が見つからなかった…
という経験をした人は少なくないはずです。そこでこの記事では、AWSでできることやパブリッククラウドの現状を理解し、AWSエンジニアになる方法をお伝えします。
AWSはAmazonが提供しているクラウドサービス
「AWS」とは、Amazonが提供するクラウドサービスの総称です。そもそもはAmazonのインフラを支えるために作られたものですが、他社にも提供しようと2006年7月に公開されました。
利用しているのは、「インターネット上で何らかのサービスを提供したい」、「インターネット上にデータを保存しておきたい」と考える企業や個人です。
AWSの基本サービスは、レンタルサーバー、データベース、ストレージを利用したデータ保存、画像認識などです。サービスの種類は大きく分けて100以上、細分化すると700以上もあり、今現在も増え続けているそうです。
種類が多くて便利な反面、多過ぎて全体像が見えにくく、具体的にどんなことができるのかがわかりにくいという一面もあります。
パブリッククラウド市場の現状と展望
パブリッククラウドとは、AWSをはじめとするクラウドコンピューティングモデルのひとつです。企業や個人など不特定のユーザーに、サーバーやストレージ、データベース、ソフトウェアなどをインターネット経由で提供します。
AWSのほかにも、Microsoft AzureやGoogle Cloudといったパブリッククラウドがあります。
総務省の令和3年版情報通信白書によると、企業におけるクラウドサービス利用状況は68.7%で、年々増加しています。そのうちの87.1%がサービスの効果を実感しているという調査結果です。
利用しているクラウドサービスの利用内訳では「ファイル保管・データ共有」が最も多くなっています。
総務省のデータセンター市場及びクラウドサービス市場の動向によると、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンプレ環境からクラウドへの移行が進み、2022年は前年比29.8%増の1,594億円でした。
パブリッククラウドは今後ますます広まっていくでしょう。AWSは日本のクラウド利用企業の半数以上が利用しており、この先も業界・業種問わず広く利用されていくことが予想できます。
なお、プログラミングを学びたい気持ちはあるものの、どの言語が自分にあうのか、どう学習を進めればいいのかなどがあいまいな人は「プログラミング学習プラン診断」をお試しください。
かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう言語や学習プランを診断してもらえます。
効率よくプログラミングを学習したい人は、ぜひ一度お試しください。
\ 4つの質問に答えるだけ /
AWSでできる5つのこと

AWSでできることを5つ紹介します。
AWSの無料枠でできることや始め方、注意点などの詳細を知りたい人は次の記事で詳しく解説してますのでぜひ参考にしてください。

Webサイト・Webサービスの構築・運用
AWSサービスを利用し、Webサイト・Webサービスの構築・運用が可能です。
クラウド上にサーバーを構築したいときにはAmazon EC2を利用します。無料でt2.microまたはt3.microインスタンスを月に750時間まで利用が可能です。使わない時間にはEC2を停止すると、無料時間を節約できます。
Amazon S3は、ストレージサービスで無料利用枠として5GBのストレージが使用できます。定期的にストレージやサービスの利用状況を確認し、無料利用枠を効率的に運用しましょう。
また、
Amazon RDSを利用するとデータベースを構築できます。Amazon RDSは、大規模なリレーショナルデータベースサービスです。
大量のデータを高速・安全に処理できるため、基幹系の業務システムにも使われています。Amazon RDSの無料利用枠は750 時間/月となります。
データのバックアップ・災害対策
AWSを利用したデータバックアップには、Amazon S3やRDSをはじめ、AWS Backupなどがあります。
AWS Backupは、設定したAWSサービスのデータを一元バックアップできるAWSサービスです。AWS Backupのサービス自体は無料で利用できますが、バックアップストレージ使用料に応じて料金がかかります。
災害対策としてAWSでは、東京リージョンや大阪リージョンなどの複数リージョンの利用が推奨されています。
リージョンより狭い範囲のアベイラビリティゾーンなどの利用も可能です。S3のクロスリージョンレプリケーションでリージョン間のデータ同期や、AWS Backupを活用することができます。
ビッグデータの蓄積・分析・運用

ビッグデータの蓄積や分析、運用にはAmazon S3やAmazon RDS、Amazon EMR、Amazon Kinesisなどを利用できます。
Amazon S3は、耐久性が高く、大容量であるため、ビッグデータの蓄積が可能です。複数のアベイラビリティゾーンに対して自動的に同期をとることができます。無料利用枠として5GBの標準ストレージがあります。
Amazon RDSはAWSサービスが提供するデータベースですが、その中でもAmazon Redshiftは高速処理が得意でビックデータ対応におすすめです。Amazon Redshiftは高速でSQLでデータクエリができます。750時間/月の無料利用枠があります。
ビッグデータの分析はAmazon EMRでできます。Amazon EMRは、大量データを分散処理しながら分析が可能で、Apache HadoopやHBaseなどの技術が使われています。初回利用時に60分の無料利用枠が提供されます。
Amazon Kinesisは、リアルタイムでのストリーミングデータ収集および処理が可能です。無料利用枠として、データ取り込み1,000,000レコードまで利用できます。
基幹・業務システムの構築
基幹業務システムの構築は、Amazon EC2やAmazon VPC、Amazon RDSで可能です。
まず、Amazon EC2でクラウド上にサーバー構築します。無料利用枠としてt2.microまたはt3.microインスタンスを750時間/月が利用可能です。
ネットワークは、Amazon VPCで設定します。仮想ネットワークでセキュリティを担保し安全に運用することができます。
最後に、Amazon RDSでMySQLやPostgreSQLなどのデータベースを構築しますdb.t2.microまたはdb.t3.microインスタンスを750時間/月が無料利用枠となります。
統合開発環境(IDE)の構築
AWSサービスの統合開発環境(IDE)は、AWS Cloud9やAWS CloudFormationなどを利用します。
AWS Cloud9は、マネジメントコンソール上で動作するIDEです。複数のプログラミング言語をサポートし、リアルタイムで複数人で編集できます。
AWS Cloud9はEC2上で稼働させることが多いため、EC2の無料利用枠を使用します。
また、AWS Cloud9のプロジェクトファイルの保存先をAmazon S3にする場合は5GBまでの標準ストレージが無料で利用できます。
なお、IT企業への転職や副業での収入獲得を見据え、独学でAWSのスキルを習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。
侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポートしてもらえます。
「受講生の学習完了率98%」「累計受講者数4万5,000名以上」という実績からも、侍エンジニアなら未経験からでも挫折なく転職や副業収入の獲得が実現できますよ。
\ 給付金で受講料が最大80%OFF /
AWSの導入事例
AWSのサービスを複数組み合わせると、より便利なサービスを作ることができます。ここからは、代表的なサービスの利用例を紹介しましょう。
シャープ株式会社

IoT家電を快適に利用するため、AWSを導入しています。
“ヘルシオをはじめとした AIoT 家電を利用するユーザーが、ストレスなく安心してCOCORO+のサービスを利用できるようにするためには、信頼性や安定性が高く、レスポンスも十分なクラウドインフラの確保が不可欠でした。”
引用元:AWS導入事例:シャープ株式会社
世界中のユーザーからアクセスが一気に集中しても、AWSのインフラは十分なレスポンスを返し続け、問題なく運用ができたとのことです。
任天堂株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー

任天堂とディー・エヌ・エーは協業で、スマートデバイス向けゲーム「Super Mario Run(スーパー マリオ ラン)」を開発しました。iOS版では150もの国と地域を対象に配信するにあたり、以下のような課題がありました。
“堅牢なシステムインフラを極めて短時間に構築することが必要でした。”
引用元:AWS導入事例:任天堂株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー
そこで、
“クラウドであればピーク時の負荷にも柔軟に対応でき、コストの最適化という意味でも大きなメリットになると考えました。
引用元:AWS導入事例:任天堂株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー
(中略)DeNAがオンプレミスで実績を積んできたアーキテクチャーを、そのままクラウド化できることでした。”
という理由から、AWSを利用することに決めました。
株式会社ジャパンネット銀行(現PayPay銀行)

ジャパンネット銀行はネット専業銀行として、インターネットを通じて320万の個人・スモールビジネスの顧客にサービスを提供していましたが、サーバー老朽化、OSの保守切れといった問題を抱えていました。そこで、他のネット専業銀行でシステムの移行実績があったことからAWSが選ばれました。
“「以前より金融機関でのクラウド活用の事例は聞いていましたが、2014年にソニー銀行様が行内システムのAWSへの移行を発表されたことには触発されました」(出口氏)”
引用元:AWS導入事例:株式会社ジャパンネット銀行
導入した結果、最短で構築できたうえにコストを抑えることができました。さらに、規模変化への柔軟な対応や、災害対策の実現を可能にしました。
なかでも費用面での効果が大きく、固定費が変動費に変わったため、データセンターの運用やハードウェアの購入費、保守費用などが削減されたそうです。
Retty株式会社

元々VPSサーバーを使用していましたが、サービスの急成長に伴い「少人数でもスピードを落とさず、スケールさせる基盤が必要」になったため、クラウド環境への移行を検討し始めました。そして、以下の理由によりAWSの利用を決めました。
“マネージドサービスの充実度、APIの充実、質の高いユーザーコミュニティから提供されている資料やツールによる運用ノウハウの蓄積。中〜大規模なWebサービスを運営するにあたって他のクラウドサービスには無い恩恵にあずかる事ができる基盤ということで決定しました。”
引用元:AWS導入事例:Retty株式会社
利用開始時からユーザー数が10倍以上になった今も安定可動できており、AWS利用のメリットを感じているようです。
なお、ITの仕事に興味はあるものの、どの職種が自分にあうのかわからない人もいますよね。そんな人は「ITキャリア診断」をお試しください。
かかる時間はたったの1分。5つの質問に答えるだけで、自分にあうIT職種を診断してもらえます。
自身に適した職種が知りたい人は、手軽に試してみると良いですよ。
\ 5つの質問に答えるだけ /
全日本空輸株式会社(ANA)

ANAでは、ビッグデータを人工知能(AI)や機械学習などの最新デジタル技術に融合させることで、分析業務の大幅な効率化・高度化を狙いました。これらを実現させるためは、「柔軟性と拡張性を備えたデータ分析基盤が必須」と考え、Amazon RedshiftとAmazon EC2、Amazon S3、Amazon Auroraなどを採用しました。
その結果、AWSをこのように評価しています。
“オンプレミス環境で運用してきたデータ分析基盤を、大きなトラブルなくクラウドに移行できました。
(中略)ヘビーユーザーほど「レスポンスが速くなった」「使い勝手が良くなった」と実感しているといいます。さらに今後、分析業務の効率化や高度化が進んでいくことも期待されています。”
引用元:AWS導入事例:全日本空輸株式会社
上記に加え、ディスク容量の拡張、バッチ処理の長時間化、運用業務の負荷などのAWS導入前の問題点も解消され、快適に運用ができているとのことです。
AWSを使う5つのメリット

AWSを使うメリットには「費用」、「高機能」、「スピードの向上」が挙げられます。具体的にはどんなメリットがあるのかを、説明していきます。
コストの最適化(従量課金制)
AWSの利用は、初期費用が不要で、利用した分だけ料金が発生する従量課金制です。一般的なレンタルサーバーの場合、通信量に関わらず毎月一定の料金がかかりますが、AWSは使った分だけ支払えばいいので、コスト削減が期待できます。
信頼性・セキュリティの高さ
信頼性とは、ネットワークなどのインフラストラクチャやサービスが障害などで中断し復旧した際に、許容できる期間内に回復できる能力です。
AWSでは、東京リージョンや大阪リージョンなど複数リージョンへの分散や同一リージョン内で複数のアベイラビリティゾーンの配置が可能です。これにより大規模災害などの地理的なリスクを分散させることができます。
また、Amazon S3やAmazon RDSはデータを自動的に他のアベイラビリティゾーンに同期できるため、データの耐障害性が高まります。
AWSのセキュリティの面では、Amazon VPCを利用すると、セキュリティやネットワークを即時に細かく制御できます。転送時と保存時のデータ暗号化にも対応しています。使用する暗号化キーも自社や個人のセキュリティレベルに合わせて選択できます。
柔軟性・拡張性の高さ
100以上のサービスを提供しており、あらゆる場面で利用できる柔軟性があります。また、サービスによって、規模を簡単に大きくしたり小さくしたりできる拡張性の高さがあります。
使用するデータの容量が大きくなったり、サービスの規模が大きくなったのでサーバーの規模を倍増させたくなったとき、一般的なサーバーなら時間や経費などのコストがかかりますが、AWSなら素早く低コストで対応できるのです。コストをかけずスピーディ、これは大きなメリットです。
導入スピードが速い
導入のスピードが速いこともAWSを使うメリットです。仮想サーバーであるAmazon EC2は、使用するストレージなどが決まれば数分で起動が可能です。
また、稼働しているシステムがアクセス集中した場合には、よりスムーズに稼働するストレージへの付け替えが即時にできます。
稼働中のAWSを別リージョンに展開したい場合はAWS CloudFormationを使用すると10分程度で構築が完了します。
システムを試験的に現行環境以外で稼働したい場合やスピードが求められている案件のシステム基盤としてもAWSは非常に有効です。
パフォーマンスの安定
常に最新のハードウェアへアップグレードされます。サーバーの安定感や反応速度が安定しており、質が常に高く保たれています。
オンプレミスからAWSに切り替えた企業では、パフォーマンスが安定した、業務スピードが改善したと回答している例は少なくありません。
AWSを使う3つのデメリット

AWSを使うメリットを3つ詳しく説明します。
サービスが豊富すぎて選定が難しい
対応できるサービスが豊富で何でもできてしまうため、どのサービスを選べばいいのか、どのようにサーバーを構築すればいいのか、専門知識やノウハウが必要になります。拡張性の高さが、逆にデメリットになっています。
毎月の料金が把握しにくい
従量課金制なので、毎月の費用が一定ではありません。例えば、 Webサイト構築のためにAWSを利用しており、テレビに取り上げられてバズったらアクセスが集中し高負荷がかかって料金が跳ね上がる……という懸念があります。
AWSに切り替えた多くの企業がコストが下がったと回答していますが、費用が固定ではないからこそ、毎月の料金が把握しづらいのは確かです。
障害・トラブル時には自己解決が必須
AWSが提供するのはインフラのみで、障害やトラブルが起こった時の対応はしてもらえません。実際、2019年8月にAWSに大規模障害が起こったとき、さまざまなサービスで緊急メンテナンスの必要が生じて、多大な影響がありました。
そんな時のために、障害対応の備えをしておかなければなりません。
AWSの知識は身につけるべきなのか
AWSの知識はその需要の高さから身につけるべき知識です。
AWSの習得を目指すのにおすすめな人の特徴を3つ紹介します。
まず、主体的に学習を進められる人におすすめです。AWSは非常に多くのサービスを提供しているため、定期的に知識のキャッチアップが必要になります。
次に、AWSは複数のサービスを組み合わせて構築するため、好奇心が旺盛な人におすすめです。また、サービスの機能追加なども頻繁に行われるので、新しいサービスに興味を持ち、実際に試してみることで知識を習得できます。
最後に、臨機応変な対応ができる人です。サービス間の連携などで意図しないトラブルが発生した場合など、柔軟な対応で早期に復旧しなければいけません。
AWSエンジニアに向いている人の特徴を次の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

AWSの使い方はどう勉強すればいい?

AWSエンジニアになるには、どのような方法で勉強すればいいのでしょう? 具体的な方法を3つ、ご紹介します。
AWSの基礎部分から学習したい人:入門書を使う
AWSエンジニアには、高い専門性が必要とされます。サーバーやデータベースの知識は必須なうえ、AWS独自の専門用語が多く、慣れるまではなかなか手強いかもしれません。
まずは、入門書を購入し、初歩的なところをしっかり抑え、徐々にレベルアップしていきましょう。
おすすめの入門書は「Amason Web Services 基礎からのネットワーク&サーバー構築 改訂版」です。
AWSの使用をイメージしながら学習したい人:AWS入門サイトを使う
二つめは、入門サイトで勉強する方法です。動画を見て勉強するサイトや、スライド形式の解説を読んでから設問を解いて学習を進めていくサイトまで、さまざまな入門サイトがあります。
実際にAWSの画面を見ながら操作や技術を学べるので、操作感がイメージしやすいのが特徴です。おすすめの入門サイトはこちらを参考にしてください。
どのサイトも基本的には無料で使えるので、閲覧してから自分に合ったサイトを選んでくださいね!
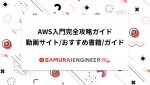
なお、IT企業への転職や副業での収入獲得を見据え、独学でAWSのスキルを習得できるか不安な人は「侍エンジニア」をお試しください。
侍エンジニアでは、現役エンジニアと学習コーチの2名体制で学習をサポートしてもらえます。
「受講生の学習完了率98%」「累計受講者数4万5,000名以上」という実績からも、侍エンジニアなら未経験からでも挫折なく転職や副業収入の獲得が実現できますよ。
\ 給付金で受講料が最大80%OFF /
「AWSを仕事にしたい!」という人:スクールでプロに習う
「AWSを使ってアプリ開発をしたい」というように、AWSを本気で仕事にしたい方は、スクールでプロに教わるのが断然おすすめです。AWSを使った仕事は、実際にAWSを仕事にしているエンジニアに習うのが一番の近道だからです。
スクールの講師は現役エンジニアが務めていることが多く、スクールによっては、転職先やフリーランスとしての案件を紹介してくれるところもあります。本気でやりたい方ほど、スクールに通うのをおすすめします。
AWSのスクールに関しては次の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。
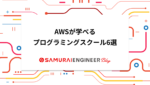
AWSに関するよくある質問
AWSに関するよくある質問を3つ紹介します。
AWSエンジニアの需要はあるのか?
AWSの利用企業は年々増加しているため、AWSエンジニアの需要も高まっています。
主な求人サイトでAWSエンジニアの求人数を2020年4月と比較してみると、次の通りでした。
未経験でも月収30万円、経験に応じて月収100万円の求人がみられます。


出典:求人ボックス
AWSエンジニアはインフラ構築がメインであるため、インフラエンジニアやネットワークエンジニアからAWSに関する知識を得てAWSエンジニアになるキャリパスが多いです。
AWSのサポートプランの内容はどんなものがあるの?
AWSサポートには複数のプランがあり、ベーシックプランであればすべてのAWSユーザーが利用可能です。ベーシックプランは基本的なサポートのみで、技術的なサポートは受けられません。
プランの料金が上がるほど、受けられるサポートレベルも上がります。
サポートプラン内容など、AWSに質問する際のポイントを次の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
AWSの練習に役立つサイトはある?
AWSの練習を通して、AWSの理解を深めたいと考えている人におすすめのサイトはAWSの公式サイトです。
AWS公式サイトでは、サービス紹介はもちろん、実際のAWS構築時に役立つベストプラクティスがドキュメントおよび動画でも掲載されています。
AWS練習に役立つサイトや効果的な学習方法を次の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ
AWSの需要は年々増加しており、AWSエンジニアの需要も比例して増加しています。
インフラの知識を基にAWSサービスを利用してクラウド基盤を構築するAWSエンジニアになるためには、まずはインフラを含むIT基礎知識の習得をおすすめします。
侍エンジニアでは、受講者だけのオーダーメイドカリキュラムだけでなく、マンツーマン指導を行うため未経験でも挫折しにくいです。また、現役エンジニアが対応するQ&A掲示板、不安や悩みを相談できる学習コーチも学習の後押しをします。
まずは無料カウンセリングで侍エンジニアにご相談ください。
無料カウンセリングで相談してみるこの記事の監修者

フルスタックエンジニア
音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。












