この記事では現役技術者の口コミも交え、インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる理由を解説します。
インフラエンジニアは「やめとけ」って噂は本当?
他のエンジニア職種の方がいいのかな?
国内におけるIT人材不足の深刻化を背景に、未経験向けのインフラエンジニア求人も増加傾向にあります。AWSを始めとしたクラウドサービスも市場規模が拡大していることから、インフラエンジニアの将来性が高いことが予想できます。
しかし、ネットやSNS上ではしばしば「インフラエンジニアはやめとけ」というワードを見かけることもあります。このような情報を見聞きすると、目指すべきか悩む人も多いですよね。
そこでこの記事では現役技術者からの口コミも交え、インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる理由を解説します。噂と実態をよく見極めたうえで、インフラエンジニアを目指すべきかも解説するので、ぜひ参考にしてください。
- インフラエンジニアは夜勤やスキルアップのしにくさから「やめとけ」と言われる
- 資格取得や実務経験を積み上流工程にいけば多くの悩みを解決できる
- 機械いじりが好きな人や好奇心旺盛な人には向いている職種のひとつ
インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる6つの理由
さっそくインフラエンジニアが「やめとけ」といわれる理由を、6つにまとめて解説します。
理由1:休日出勤や夜勤がある
インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる理由のひとつに、夜勤や休日出勤の多さが挙げられます。
インフラの運用には24時間365日体制が求められ、システムの監視や障害対応は止まることが許されない業務です。したがって、夜間に監視業務を行うだけでなく、突発的なトラブルが発生した際には休日出勤が必要なケースもあります。
また、定期的なメンテナンスやアップデートも、ユーザーへの影響を避けるため、深夜や週末に実施されることが一般的です。通常の勤務時間外に作業が集中することも多く、不規則な生活リズムになりがちです。
夜勤や休日出勤が多い勤務体制は、プライベートとの両立が難しくなる要因にもなり、家族や友人との時間が取りづらくなることもあります。
肉体的・精神的なストレスが蓄積しやすいため、「長く続けるのは厳しい」と感じる方もいるようです。
現役のインフラエンジニアからも、「夜勤や休日出勤がつらい」といった声が多く聞かれ、働き方の厳しさを物語っています。
なお、次の記事ではインフラエンジニアになって後悔したことを詳しく解説しているので、よければ参考にしてください。

理由2:ルーチンワークが多く仕事がつまらない
インフラエンジニアの運用・保守業務を担当するポジションでは、日々の業務がルーチン化しやすく、仕事にやりがいを感じにくいという声も聞かれます。
具体的には、サーバーやネットワークとログの監視、障害発生時のマニュアル対応など、決められた手順を繰り返す業務が中心となるため、技術的な成長を実感しづらいケースもあります。トラブルが発生しない日は、ほとんどやることがなく時間を持て余してしまうという現場も少なくありません。
あまりにも単調な作業が続くと、「このままでスキルは伸びるのか?」「自分は本当にエンジニアとして成長しているのか?」と不安も出てくるものです。
事実、ルーチンワークがつらいと感じているインフラエンジニアもいます。
クリエイティブな要素や新しい技術に触れる機会も少ないため、IT業界の魅力に惹かれて入った人ほど、理想とのギャップを感じやすいでしょう。
もちろん、すべてのインフラエンジニアが同じわけではなく、設計・構築といった上流工程を目指せばやりがいのある仕事に就くことも可能です。
ただし、最初のキャリアとして運用・保守からスタートするケースが多いため、「同じ作業の繰り返しが苦手な人」にとってはストレスになる可能性もある点は押さえておきたいところです。
理由3:労働に見合う給料がもらえない
労働に見合う給料を得にくい点も、インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる理由の一つです。口コミにおいても給料の低さを指摘する声が見られています。
実際に求人情報を見てみると、インフラエンジニアの初年度の月収20万円程度に設定されているケースが多く、年2回の賞与を加味しても300万円程度となることが一般的です。



夜勤や休日出勤がある場合は、手当が支給されるためより多く稼ぐことも可能です。ただし、なかには夜勤手当や休日手当が既に給料に組み込まれているケースもあるので事前に確認しましょう。
理由4:日々勉強する必要がある
インフラエンジニアとして働く上で避けて通れないのが、継続的な学習です。テクノロジーの進化が早いIT業界では、常に最新の知識を追いかけ続ける必要があり、それが「やめとけ」と言われる理由にもなっています。
インフラエンジニアの中でも勉強が嫌いな人にはつらいという声があるのも事実です。
例えば、従来のオンプレミス環境からAWSなどのクラウドサービスへ移行が進む中で、クラウドの設計・構築スキルは今後インフラエンジニアにとって必須となる可能性が高いです。
一方で、インフラの運用作業ではPythonやShellを使った自動化のニーズも高まっており、スクリプト言語の習得も欠かせません。
常に学習する姿勢を持たなければ上記のスキルを身に付けることはできず、市場価値を維持できない点で、やめとけという声が挙げられています。
理由5:成果が評価されにくく昇給しづらい
インフラエンジニアは、「成果が見えにくい職種」として知られており、そのために昇給や評価が得られにくいという悩みを抱える人も少なくありません。
理由として、インフラの仕事は「システムが正常に稼働していること」が最大の成果である点が挙げられます。
口コミに記載のあるとおり、トラブルが起きないこと=仕事ができていることを意味するため周囲からはその努力や技術力が見えづらく、評価されにくいのが現実です。
また、インフラエンジニアはアプリやWebサービスのように新機能の開発やプロダクトリリースといった目に見える成果を出す機会が少ないため、社内外でのアピールが難しいという面もあります。
特に運用や保守といった下流工程に留まっている間は、組織内での立場も固定化されやすく、キャリアの停滞を感じることもあるでしょう。
理由6:スキルアップしにくい
先述のとおり、インフラエンジニアは業務の大半が単純作業であるため、スキルアップの実感が得にくいことから「やめとけ」と言われています。
例えば、システム監視や障害対応・定型的な報告作業など、決まったフローを繰り返すだけの業務に追われる現場では成長の実感が得られにくいという声もよく聞かれます。
また、新しい技術を業務で試す機会も限られているため、スキルアップには自発的な学習が不可欠です。最新のクラウド技術やインフラ自動化スキルなどを身につけるには、業務外の時間を使って参考書を読んだりハンズオンで仮想環境を構築したりといった自主的な努力が求められます。
このような環境において、向上心がないと「気づけば何年も同じ作業ばかりやっていた…」という事態になりかねません。
【現役技術者に聞いた】インフラエンジニアの実態

前述したやめとけといわれる理由を交え、ここからはインフラエンジニアの実態を解説します。
労働時間は長くなく残業も少なめ
「インフラエンジニアは大変そう」というイメージを持たれがちですが、実はシフト制を採用している現場が多く、残業が少ない傾向にあります。
とくに監視や運用のポジションでは、決まった時間に業務を引き継ぐスタイルが基本となっており、勤務時間が厳格に管理されているケースが多いです。
また、システムが安定して稼働していれば定時で業務が終わることも珍しくなく、突発的な障害対応やメンテナンス作業さえなければ、ワークライフバランスを保ちやすい職種ともいえます。夜勤や休日出勤がある分、代休や夜勤明けの休みがしっかり取れる環境が整っている職場も増えてきました。
インフラエンジニアの間でも意外と働きやすい職場環境であると評価されることもあります。
Xより引用
インフラエンジニアは残業が少ない職種のひとつ トラブルが起きなければ基本的に業務は安定してる 大手企業では運用自動化ツールも導入されて効率アップ だから、働きやすさ重視ならインフラ系はかなりアリ
もちろん、緊急トラブルが発生した際はイレギュラーな対応が求められる場面もありますが、それさえなければ、予測しやすく安定した働き方が可能です。
上流工程が担えるようになれば夜勤はほぼない
インフラエンジニアとして経験を積み、設計・構築といった上流工程を任されるようになると、夜勤や休日出勤はほとんど発生しなくなります。
上流工程はシステムの要件定義や設計・構築時の計画立案などが中心であり、日中の業務時間内にクライアントや他の技術者と連携をとる必要があるため、自然と日勤中心の働き方になります。
下流工程と比較して生活リズムも整いやすく、体調管理がしやすい環境です。事実、インフラエンジニアの方の中には、夜勤を辞めたいのであれば上流工程に行くべきだと述べている人もいます。
さらに、インフラエンジニアとしての経験は、クラウドエンジニアやセキュリティエンジニアといった発展的な職種に活かせます。例えば、AWSやAzureを使ったクラウド環境の設計構築や、システム全体のセキュリティ対策を講じる業務では、物理・仮想問わずインフラの基礎知識が欠かせません。
下流工程から上流工程へのキャリアアップを実現することで、働き方そのものが大きく改善されるだけでなく、年収アップや専門職への転身という選択肢も広がります。
「夜勤がつらい」「不規則な働き方を変えたい」と感じているなら、上流工程を目指してスキルを磨くことが、未来を変える第一歩といえるでしょう。
インフラエンジニアとクラウドエンジニアの違いをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

緊急対応はやりがいが大きい
インフラエンジニアの業務のなかでもとくにプレッシャーがかかるのがシステム障害時の緊急対応です。システムが突然停止したり、ネットワーク障害が発生した場合、一刻も早く原因を特定し、復旧させなければならない状況に直面します。
緊急対応はたしかに緊張を伴い、深夜や休日でも呼び出されることがあるため、「大変」という印象を持たれることが多いです。しかし、実はインフラエンジニアならではのやりがいを感じられる瞬間でもあります。
障害対応を迅速かつ的確に行い、システムを復旧させたときの達成感は大きく、「自分の手でサービスを守った」という実感を得られるという声も見られます。
復旧が遅れると顧客の資産や企業活動に大きな影響を及ぼす可能性もあるなかで活躍できることは、社会インフラを支える使命感も持てるでしょう。
日常のルーチン業務では味わえない、「緊急時だからこそ発揮できる自分の価値」を体感できるのは、インフラエンジニアならではの魅力といえます。
上記を含め、インフラエンジニアのやりがいをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

実務経験・実績を積めば高年収も狙える
インフラエンジニアは「年収が低い」と言われがちですが、それはあくまでキャリア初期の話です。スキルや資格、そして実務経験を積み重ねていけば、年収500万円以上を狙うことも十分に可能です。
例えば、Cisco Japanが2013年に公開した給与調査によれば、ネットワーク関連の初級資格であるCCNA保有者の平均年収は500万円を超えていたというデータがあります。

上記はやや古いデータではあるものの、業界内におけるCCNAの重要性に変化がないことから、CCNA取得で年収アップができる可能性が高いです。
また、実務経験が高ければより高年収の求人に挑戦することもできます。事実、求人サイトで実務経験ありの求人を探すと最低でも年収450万円程度を設定しているケースが多く見られます。

事実、実務経験を積み重ねた人は高年収も多いという声も見られます。
地道な努力を積み重ねて実務経験や資格などの実績を積み上げれば、より高年収を目指すことは十分可能です。
年収1,000万円を目指す方法も含め、インフラエンジニアの平均年収をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
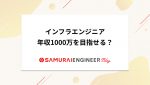
今後も将来性は高い
インフラエンジニアは、今後も将来性が高い職種といえます。とくに注目すべきは、クラウドの普及とITインフラの自動化です。
企業の多くがオンプレミスからAWSやAzureといったクラウド環境に移行を進める中で、クラウドインフラの構築・運用に精通したエンジニアの需要は年々増加しています。
また、Pythonなどのスクリプト言語を用いた運用自動化のスキルも、現場では高く評価されるようになっています。クラウドやスクリプト言語のスキルを持つことで、ただのオペレーション担当から脱却し、より付加価値の高い業務を担うことが可能です。
インフラエンジニアの中でもとくにAWSは将来性が高いスキルとして評価されています。
なお、未経験から挫折なくインフラエンジニアへの就業とAWSのスキル習得が両立できるか不安な人には、侍エンジニアの「転職保証コース」がおすすめです。
転職保証コースでは、未経験からインフラエンジニアに必要なクラウド設計や自動化システムの導入方法などを習得できます。
学習は現役エンジニアと学習コーチの2名体制でサポート。就職活動もIT企業で人事経験のあるキャリアアドバイザーから支援が受けられます。
これまで4万5,000名以上の受講生を指導しており「転職成功率99%」の実績を誇る侍エンジニアなら、未経験からでも挫折なくAWSが扱えるインフラエンジニアになれますよ。
インフラエンジニアにはなるべきなのか

これまで解説してきたとおり「やめとけ」と言われることもありますが、次のような人はインフラエンジニアがおすすめといえます。
- 機械いじりが好きな人
- 物事を論理的に考えられる人
- 堅実で責任感のある人
- 好奇心が旺盛で新しい技術に興味を持てる人
- コミュニケーション能力が高い人
インフラエンジニアはサーバーやネットワークといった機器を扱うことが多いため、機械を触ることに楽しさを感じられる人には最適です。また、障害対応や設計業務では、冷静に情報を整理して判断する論理的思考力も重要です。
安定運用が求められる職種のため、慎重さや責任感を持って物事に取り組める人ほど信頼される傾向があります。クラウドや自動化ツールなど新しい技術に積極的に触れたいという好奇心があれば、スキル習得も早く、重宝される存在になれるでしょう。
また、インフラエンジニアは他の部門や非エンジニアとの連携も多いため、相手に応じてわかりやすく説明できるコミュニケーション能力があるとより活躍の場が広がります。
インフラエンジニアがどんな人に向いているのか、その特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
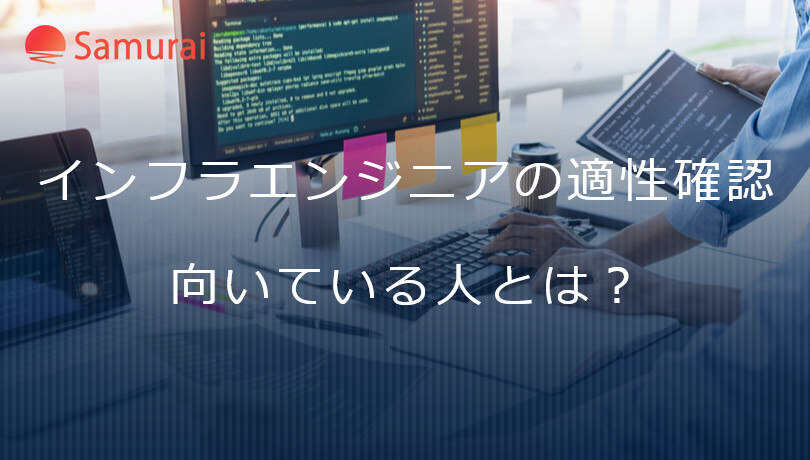
インフラエンジニア以外に魅力的なIT職種

なかには、ここまで記事を読み「目指すのはインフラエンジニアでなくても良いかも」と感じた人もいますよね。
実のところ、インフラエンジニア以外にもIT業界には魅力的なエンジニア職種が数多く存在します。そこでここからは、インフラエンジニア以外におすすめのIT職種を、厳選して3つ紹介します。
システムの設計・開発を手掛ける「システムエンジニア」
システムエンジニア(SE)は、クライアントの要望に基づいてシステムを設計し、開発の進行を管理する職種です。システムエンジニアの仕事内容や使用する言語、メリットを次の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 仕事内容 | システムの要件定義・設計、プログラマーとの連携による開発指示 |
| 使用する言語例 | Java、C#、Pythontなど |
| 主なメリット | ・開発の上流工程に携われる ・顧客と直接やり取りできるやりがい ・論理的思考と対人スキルを活かせる |
プログラミングだけでなく、クライアントとの打ち合わせや仕様書の作成など、対人スキルや計画力も求められる点がSEの特長です。自分の設計したシステムが動く喜びや、チームでプロジェクトを動かす達成感がやりがいとなります。
システムエンジニアの仕事内容をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
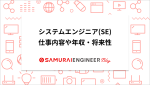
EC・Webサイトの制作を担う「Webエンジニア」
Webエンジニアは、企業のホームページやECサイト、Webサービスなどの制作・運用を担う職種です。主にユーザーが触れる部分であるフロントエンドと、サーバーやデータベースとのやり取りを行うバックエンドの両方を扱います。
| 項目 | 内容 |
| 仕事内容 | Webサイト・Webサービスの開発、UI/UX改善、API連携など |
| 使用する言語例 | HTML/CSS、JavaScript、PHP、Ruby、TypeScriptなど |
| 主なメリット | ・個人開発や副業にも活かせる ・成果が見えやすい ・最新技術を試しやすい |
Webエンジニアはとくに成果物がユーザーに直接届くため、デザインや使いやすさへの工夫がダイレクトに評価されやすいのが魅力です。また、フリーランスとして独立しやすい職種でもあり、副業や在宅勤務など多様な働き方も実現しやすい傾向にあります。
Webエンジニアの仕事内容をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

大量のデータをビジネスに活かす「データサイエンティスト」
データサイエンティストは、企業が保有する大量のデータを活用して課題解決やビジネス戦略の立案に貢献する職種です。AIや機械学習の技術を用いて、データから有益な洞察を導き出します。
仕事内容や言語、メリットは次の表を参考にしてください。
| 項目 | 内容 |
| 仕事内容 | データの収集・分析、モデル構築、レポート作成、AI導入の支援など |
| 使用する言語例 | Python、R、SQLなど |
| 主なメリット | ・AI・機械学習に関われる ・高収入が期待できる ・業界を問わず活躍できる |
データサイエンティストはとくに論理的思考力と統計的知識、プログラミングスキルが求められる高度な職種です。その分、専門性が高く、高収入やグローバルな活躍のチャンスもあります。
業界を問わず需要が拡大しているため、将来性が高いのも魅力です。データサイエンティストの仕事内容をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤を支える専門家として高い需要があります。
クラウドやセキュリティ、ネットワークなど、絶えず進化する技術を身につけることで、大規模プロジェクトへの関与や専門的なキャリア成長の機会が広がります。プロジェクトマネージャー、コンサルタント、スペシャリストなどの道を選びながら、企業のインフラ戦略を導く役割を担える未来が待っているのです。
本記事の解説内容に関する補足事項
本記事はプログラミングやWebデザインなど、100種類以上の教材を制作・提供する「侍テラコヤ」、4万5,000名以上の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」を運営する株式会社SAMURAIが制作しています。
また、当メディア「侍エンジニアブログ」を運営する株式会社SAMURAIは「DX認定取得事業者」に、提供コースは「教育訓練給付制度の指定講座」に選定されており、プログラミングを中心としたITに関する正確な情報提供に努めております。
参考:SAMURAIが「DX認定取得事業者」に選定されました
記事制作の詳しい流れは「SAMURAI ENGINEER Blogのコンテンツ制作フロー」をご確認ください。
この記事の監修者

フルスタックエンジニア
音楽大学卒業後、15年間中高一貫進学校の音楽教師として勤務。40才のときからIT、WEB系の企業に勤務。livedoor(スーパーバイザー)、楽天株式会社(ディレクター)、アスキーソリューションズ(PM)などを経験。50歳の時より、専門学校でWEB・デザイン系の学科長として勤務の傍ら、副業としてフリーランス活動を開始。 2016年、株式会社SAMURAIのインストラクターを始め、その後フリーランスコースを創設。現在までに100名以上の指導を行い、未経験から活躍できるエンジニアを輩出している。また、フリーランスのノウハウを伝えるセミナーにも多数、登壇している。











Xより引用