インフラエンジニアになるためのおすすめの本が知りたい
インフラエンジニア向けの本はどのように選べばいいの?
インフラエンジニアに興味を持ち、本で学習しようと思ったものの、実際にどんな本を選んだらよいのかわからない人もいますよね。
そこでこの記事では、インフラエンジニア向けのおすすめ本を分野別に21冊紹介します。最後まで読めば、効率のよい学習方法もわかりますよ。
インフラエンジニアに必要な知識を学べる本を知りたい方は、ぜひご覧ください。
インフラエンジニアとは
インフラエンジニアとは、システムやインターネットを使用するために必要な、ネットワークやサーバーを構築するエンジニアのことです。
ネットワークの構築では、次のような作業を行います。
- 接続機器やLANを使ったコンピューター同士の接続
- 各コンピューターへのIPアドレスの割り振り
- インターネットへの接続
サーバーの構築では、さまざまな機能を持つサーバーのシステムを形成します。サーバーの機能の例としては、次のようなものがあります。
- データの保管
- データの処理
- データの提供
つまりインフラエンジニアは、さまざまなシステムを構築し、それを使うためには欠かせない職業だと言えます。
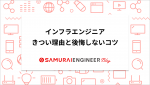
初心者におすすめのインフラエンジニア向け本一覧
インフラエンジニアには、次の3つの種類があります。
- サーバーエンジニア
- ネットワークエンジニア
- クラウドエンジニア
サーバーエンジニアとネットワークエンジニアは、上記でも紹介したようにそれぞれサーバーやネットワークを構築するのが仕事です。さらに、近年のクラウドサービスの広がりによって、クラウドを使ったサーバーやネットワークの構築を行うクラウドエンジニアも登場しました。
どのインフラエンジニアを目指す場合も、さらにはインフラエンジニアになってからも、スキルアップのための勉強は欠かせません。さまざまな学習方法がありますが、独学の場合には本を使って学習するのもひとつの方法です。
ここでは、学習できる内容ごとにインフラエンジニア向けのおすすめ本を一覧で紹介します。
インフラ全般の勉強に役立つ本4選
インフラ全般の勉強に役立つおすすめ本は次の4冊です。
- インフラエンジニアの教科書
- サーバ/インフラエンジニアの基本がこれ1本でしっかり身に付く本
- 絵で見てわかるITインフラの仕組み 新装版
- 絵で見てわかるOS/ストレージ/ネットワーク 新装版
それぞれ、詳しく紹介します。
インフラエンジニアの教科書
実際にインフラの管理・運用に携わる著者が、インフラエンジニアの仕事内容や必要な知識・スキルなどを解説した本。インフラエンジニアの世界に興味がある非エンジニアが参考にできる内容です。
サーバーやOS、ネットワーク機器だけでなく、購買や商談などに関するスキルについても言及。基礎知識から実践まで、濃密な内容をこの一冊で学べます。
サーバ/インフラエンジニアの基本がこれ1本でしっかり身に付く本
サーバー・インフラの運用・管理などに携わるエンジニアにとって必要な技術や知識を、基本から解説した本。学習法やスキルアップ、業務知識、職業倫理などについても解説されています。
サーバーやネットワークの管理・運用業務に携わることになった人、サーバー/インフラエンジニアとしての基本をしっかり身につけたい人におすすめ。近年求められることが多くなった、クラウドを扱うために必要な知識もフォローしています。
絵で見てわかるITインフラの仕組み 新装版
ITインフラという領域全体を、ミクロ・マクロの視点からわかりやすく絵を使って解説。ITインフラの常識を学ぶことで、技術の本質を理解できる基礎力が身につきます。
ITに関わる仕事を始めて5年目くらいまでのエンジニアを対象に、ITインフラ全般を学べる内容で構成。インフラに関わる仕事をしたい人はもちろん、他の専門領域の人でも役立てられる一冊です。
絵で見てわかるOS/ストレージ/ネットワーク 新装版
企業システムにおけるOS・ストレージ・ネットワークといった重要なITインフラ技術について、絵を多用してわかりやすく解説した本。難解なインフラ技術を俯瞰できるような図と解説が掲載されており、実際の業務システム開発や保守運用にも活かせるノウハウが満載です。
データベース管理やアプリケーション開発経験のある若手エンジニアや、ネットワーク管理に初めて挑戦するエンジニアにおすすめ。抽象的な技術概念を可視化しながら、データベースにおけるデータの入出力やハードディスク、メモリなどの役割/動作を解説しています。
サーバーの勉強に役立つ本4選
サーバーの勉強に役立つおすすめ本は次の4冊です。
- イラスト図解式 この一冊で全部わかるサーバーの基本
- ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用ガイド 動かしながら学ぶWebサーバーの作り方
- 絵で見てわかるWindowsインフラの仕組み
- 本気で学ぶ Linux実践入門 サーバ運用のための業務レベル管理術
それぞれ、詳しく紹介します。
イラスト図解式 この一冊で全部わかるサーバーの基本
クラウドとオンプレミスの連携や使い分けなど、これからサーバーにかかわる人が知っておきたい知識をまるごと解説した本。すべての項目で解説を徹底的にイラスト図解化し、わかりやすさにこだわっているため、実務に活かせる知識が確実に身につきます。
楽しく知識を身につけられるよう工夫されているので、知識ゼロから学習を始める人にもおすすめ。よく使う用語の意味や技術の仕組みをスムーズに学べる一冊です。
ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用ガイド 動かしながら学ぶWebサーバーの作り方
Linuxの基礎からセキュリティまで、Webサーバーを運用するために身に着けるべき知識をまとめた本。Linuxのインストールからスタートし、最終的にはDockerでコンテナの作成まで習得できます。
実際に手を動かして、Webサーバーを構築・運用しながら学習を進めるので、初心者でもわかりやすいのがポイント。巻末付録には、サーバーを運用するために使われやすいコマンドを厳選して集めたコマンドリファレンスがついています。
絵で見てわかるWindowsインフラの仕組み
Windows Serverをはじめとした製品群でシステムを構築するための解説書で、主に絵で解説されていて初心者にも理解しやすい構成になっています。Microsoft社が提供している各サーバー製品やサービス、クラウドサービスについての概略と特徴を理解できます。
Windowsシステムインフラ向けの機能に触れた経験があるにも関わらず、全容をつかめないと感じている人にもおすすめ。普段なにげなく使っているWindowsシステムについて、全体像を把握できるような内容です。
本気で学ぶ Linux実践入門 サーバ運用のための業務レベル管理術
Linuxの基礎知識を学びながら、実用的な操作・設定・管理方法を身につけられる実践的な入門書です。しっかりと実践的な知識を身に着けることで、初心者から一歩先に進めます。
Linuxの基本的な使い方から、日々の管理業務で求められる各種操作までを覚えられる一冊。業務に使用するコマンドの実行例が多数掲載されていて、必要なコマンドを学習できます。
ネットワークの勉強に役立つ本5選
ネットワークの勉強に役立つおすすめ本は次の5冊です。
- ネットワークはなぜつながるのか 第2版 知っておきたいTCP/IP、LAN、光ファイバの基礎知識
- マスタリングTCP/IP 入門編
- [改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座
- インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版
- インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン
それぞれ、詳しく紹介します。
ネットワークはなぜつながるのか 第2版 知っておきたいTCP/IP、LAN、光ファイバの基礎知識
ブラウザにURLを入力してからWebページが表示されるまでの道筋をたどって、その裏側で動くTCP/IPやLAN、光ファイバーなどの技術について解説した本。機器やソフトウェアの動きと連携を知ることで、ネットワーク全体の動きがわかるような解説がなされています。
身近な題材を使って解説が進められていることで、理解が進みやすいことが特徴。基礎的な内容が多く解説されていることに加え、大事な点は要約としてまとめられているので初心者でも理解しやすい一冊です。
マスタリングTCP/IP 入門編
豊富な脚注と図版・イラストを用いたわかりやすい解説により、TCP/IPの基本をしっかり学べる本。プロトコル、インターネットやネットワークについて理解を深めるための第一歩として活用できます。
時代の変化に即したトピックが加えられているので、新しい知識を求める人にもおすすめ。ベストセラーとなるだけの実績がある本なので、手元において何度も読み返すのもよいでしょう。
[改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座
博士とネット君というキャラクターを用いて、ネットワークの仕組みを基礎の基礎から解説した本。1講座3分を目安に作られているので隙間時間でも学びやすく、頭の中がすっきり整理されます。
おもしろさに重点をおいた解説で、楽しみながら読み進めやすいのもポイント。ネットワークの勉強が難しくてなかなか進まないと感じている人におすすめの一冊です。
インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門 第2版
オンプレミスなサーバーサイトのネットワーク構築に必要な基礎技術と設計のポイントを、実際の構成例をもとに解説した本。ネットワークトラフィックの加速度的な増加に伴って需要が高まっている高化設計や最適化設計についても解説されています。
クラウドとオンプレミスの共存環境は進みつつありますが、そんな中でも実務に耐えられるような知識が詰まった一冊。400以上の図を使って解説されているので、視覚的に理解を進められます。
インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン 実務で使えるネットワーク構成の最適解27
現代のネットワークを社内LAN、インターネット接続、サーバLAN、拠点間接続の4つに分け、それぞれの構成の最適解を提示した本。機器構成設計や経路冗長化設計など、詳細に解説された、エンジニアの実務に耐えられる一冊です。
基礎知識と現場で目にすることが多いネットワーク構成とのギャップを埋めるような内容を解説。さらに、トラブル事例やその原因、運用管理に役立つTipsなども紹介されています。
クラウドの勉強に役立つ本3選
クラウドの勉強に役立つおすすめ本は次の3冊です。
- クラウドエンジニア養成読本
- Amazon Web Services 基礎からのネットワーク&サーバー構築 改定3版
- 図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書
それぞれ、詳しく紹介します。
クラウドエンジニア養成読本
大手クラウドサービスの全体像や、現場でクラウドを活用している各種企業の事例などを紹介した本。新人エンジニアや、これからクラウドベースのシステムに取り組むエンジニアにおすすめの一冊です。
これからの最新クラウド活用やクラウドベースのシステムの全体把握をしたいと考えている人に最適。クラウドの構築と運用のノウハウが詰まっています。
Amazon Web Services 基礎からのネットワーク&サーバー構築 改定3版
代表的なクラウドサービス「Amazon Web Services」を実機代わりにネットワークを学び直すことをコンセプトとしてまとめた本。インフラ技術とAWSの知識が同時に学べる、若手技術者向けの一冊です。
自分でネットワークやサーバーを構築できるようになることを目的として設定。インフラを学びたい人はもちろん、インフラを学びなおしたいアプリ開発者にも適しています。
図解即戦力 Amazon Web Servicesのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書
Amazon Web Servicesのしくみや関連技術、クラウドとネットワークの基礎技術などについて図解を用いて解説した本。AWSのサーバーやネットワークのサービスについて、具体的なサービス名を挙げながら初心者向けにわかりやすく解説しています。
用語解説がついているなど、わかりやすさに重点をおいているため、用語が難しいと感じていた人でも安心して学べる一冊。IT業界などへの転職・就職を目指す人向けの書籍です。
セキュリティの勉強に役立つ本5選
インフラを扱うためには、外部からの攻撃や内部での不正を防ぐためセキュリティの知識も必要です。セキュリティの勉強に役立つおすすめ本は次の5冊です。
- 図解まるわかり セキュリティの仕組み
- 情報セキュリティの基礎知識
- イラスト図解式 この一冊で全部わかるセキュリティの基本
- おうちで学べるセキュリティのきほん
- 動かして学ぶセキュリティ入門講座
それぞれ詳しく紹介します。
図解まるわかり セキュリティの仕組み
攻撃の種類や対策方法、組織体制についてすべて図解を用いて解説された、管理者にも開発者にも役立つ基本がわかる本。見開きで1つのテーマを取り上げて解説しているため、気になるテーマについてピンポイントで学ぶのにも使いやすい一冊です。
知識を学べるだけでなく、考え方から技術・運用方法までを網羅している点が特徴。企業や個人のセキュリティ対策はもちろん、資格試験のための勉強にも役立ちます。
情報セキュリティの基礎知識
情報セキュリティを複雑に構成する個々の要素技術を、イラスト図解でやさしく解説した本。リスクや脅威だけではなく、それを取り巻く技術や仕組みから解説されています。
しくみや背景が年々複雑化し、何に注意すれば良いかすらわかりにくくなったセキュリティについて、わかりやすく説明。安全で快適なIT生活を送るためにも読んでおきたい一冊です。
イラスト図解式 この一冊で全部わかるセキュリティの基本
なぜセキュリティが必要なのか、どのようにしてセキュリティは確保されているのかといった仕組みを、重要用語とともに図解で解説した本。セキュリティの基礎知識について「防御」「観測」「攻撃」の3つに分類して解説されています。
さらに、セキュリティ関連の法律に関しても言及。基本知識を幅広く学ぶことで、セキュリティの全体像をつかめるような一冊です。
おうちで学べるセキュリティのきほん
セキュリティの基本から最新動向までをすべて解説し、攻撃や対策について手を動かしながら学べる本。自宅のPCでもできる実習や、章ごとに用意された確認問題を使って理解を深められる一冊です。
過去の攻撃事例を元に学習を進めていくことで、より実践的な知識を身につけられることが特徴。知識を持って現場に立つことで、セキュリティに関するトラブルを回避できる可能性もあります。
動かして学ぶセキュリティ入門講座
基礎的な知識から、現場のプロが実際に利用しているツールによる予防・対策方法までを、豊富な図解と共に、優しく丁寧に解説した本。実際にインストールして動かしながら、攻撃の手口や怪しい動作の見抜き方などを学べます。
セキュリティのプロが使うツールを使って実践するので、予防や対策のポイントと同時にツールの使い方も学習可能。セキュリティ技術者を目指す人や企業のネットワーク管理者、パソコンのセキュリティを高めたい人などにおすすめです。
インフラエンジニアのスキルを効率よく学ぶなら転職コースがおすすめ
インフラエンジニアのスキルを効率よく学ぶなら、本を使った学習だけでなくプログラミングスクールを活用するのもおすすめです。プログラミングスクールを利用すると、必要な知識を体系的に学べるだけでなく、疑問をすぐに解決できて挫折率が下がります。
SAMURAI ENGINEERの転職コースでは、インフラエンジニアに必要な知識やスキルを習得可能。経験豊富な講師によるマンツーマンレッスンで、AWSの資格も取得できます。
2021年度の実績では、転職成功率98%、平均年収は65万円アップ。無料カウンセリングを実施していますので、少しでも気になる方はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
インフラエンジニアには、サーバーやネットワークに加えセキュリティに関する知識を求められます。知識を身につけるためにはさまざまな勉強方法があり、本を使った学習は独学に向いている方法です。
まずは、自分が興味のある分野の本から手にとって見るとよいでしょう。この記事を参考に、インフラエンジニアに必要な知識を学べる本を探してみてください。
インフラエンジニアについては、下記記事でも詳しく紹介しています。あわせて参考にしてください。











