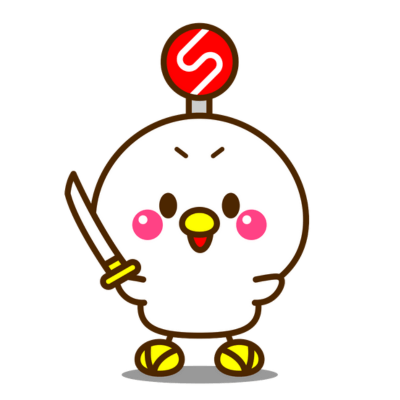2022年度に入学する高校1年生から、年次進行で高校のプログラミング教育が必修化されます。これまでも選択科目としてプログラミングの授業はありましたが、今後は高校を卒業するすべての生徒がプログラミングについて学ぶことになるのです。
高校のプログラミング教育は小学校・中学校と比べて難度が高いのか、プログラミング言語を学ぶのか、明確にわからない方もいるでしょう。
この記事では文部科学省が公表する資料をもとに、高校のプログラミング教育の具体的な内容や実践例、必修化の背景について解説します。
- 高校のプログラミング教育は必修の情報Ⅰと選択の情報Ⅱで構成される
- 情報Ⅰでは情報モラルや情報技術・プログラミングなどを学習する
- 思考力や学習への積極性などを育むのがプログラミング教育の狙い
高校のプログラミング教育は「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」で行われる

高校のプログラミング教育は、必修科目である「情報Ⅰ」と選択科目の「情報Ⅱ」で行われます。
この記事では、高校生全員が履修する情報Ⅰについて解説します。
小中学校のプログラミング教育との関係性

高校のプログラミング教育は、小学校・中学校の学習内容と関連しています。
内容は、小中学校より難度が高くなります。教える側の教員も、生徒たちが小中学校のプログラミング教育でどのようなことを学んできたのかを理解しておかなければいけません。
参考:小中高等学校のつながりを意識した小学校プログラミング教育の充実
その他の授業とプログラミング教育
高校のプログラミング教育は、「情報Ⅰ」と「情報Ⅱ」以外の教科でも行われます。
文部科学省は、高校のプログラミング教育を「情報の授業に限って行うのではなく、教科の特質に応じて横断的にスキルを身に付ける」としています。
特に、プログラミングの統計に関するスキルは数学科、情報モラルの知識は公民科、といった具合に関連が深い教科で学びます。
高校のプログラミングの授業内容

高校のプログラミング教育のなかでも、必修科目となっている「情報Ⅰ」について、どんなことを学ぶのか見ていきましょう。
具体的な学習内容は、下記の4つの項目です。
- 情報社会の問題解決
- コミュニケーションと情報デザイン
- コンピュータとプログラミング
- 情報通信ネットワークとデータの活用
それぞれ、どのような授業なのか簡単に解説します。
情報社会の問題解決
「情報社会の問題解決」では、情報社会の現代において情報技術が人や社会にどのような影響をもたらすのか、情報モラルや情報技術の役割について学習します。
コミュニケーションと情報デザイン
「コミュニケーションと情報デザイン」では、メディアごとの特徴やいろいろなコミュニケーション手段や情報デザインの考え方や表現スキルを学びます。
なお「情報デザイン」とは、情報をわかりやすく他者に伝えるための表現手法のことです。
コンピュータとプログラミング

「コンピュータとプログラミング」はその名前のとおり、プログラミングを行う授業です。
コンピューターの仕組みやシミュレーション、アルゴリズム、プログラミングなどの学習をします。
情報通信ネットワークとデータの活用
「情報通信ネットワークとデータの活用」では、情報通信ネットワークの設計と構築に関する学習を行うとともに、データの活用法についても学習します。
情報Ⅰだけでなく、数学Ⅰと連携を取った統計手法などの学習も行います。
高校のプログラミング教育で学ぶ言語の例

高校のプログラミング教育では、プログラミング言語についても学びます。
高校のプログラミング教育の学習指導要領には、言語の指定がありません。各学校が、教科書に掲載されている言語のなかから選択します。
2021年の教科書検定に合格した「情報Ⅰ」の教科書には、「Python」や「JavaScript」といった言語が掲載されています。文部科学省による教員研修用教材にはPythonを使ったプログラミングの授業例が掲載されているため、Pythonを使う学校が多いと予想されます。
高校のプログラミング教育実践例

高校のプログラミング教育は、実際、どのように行われるのでしょうか。
文部科学省による「高等学校「情報」実践事例集」から、必修科目の「情報Ⅰ」に関する実践例を抜粋して紹介します。
情報技術の発達と人への影響
「情報技術の発達と人への影響」は、メディアの利用時間やインターネットの利用状況などの調査結果をもとに、年齢や所属世帯年収別の情報格差、コミュニケーション手段の違いによるギャップなどを考える授業です。
個人でデータを確認してグラフを作成した後、グループで意見を統一して発表します。グラフ作成能力や、情報技術の発展に伴う社会の変化について主体的に考えて課題を解決する力が身につきます。
防災アプリをつくろう

「防災アプリをつくろう」は、地域の特性を踏まえた防災アプリを作る授業です。
グループごとにアイデアをまとめ、プロダクト開発に利用される「デジタルプロトタイピングツール」で、防災アプリの試作品を作ります。
デジタルプロトタイピングツールの使い方や、他者とのアイデアの共有と意見交換、課題解決のための仮説・検証スキル、試作品のプレゼンテーションスキルが身につきます。
ライフゲームをプログラミングしよう
「ライフゲームをプログラミングしよう」は、Pythonの開発環境で社会現象や自然現象をモデル化した「ライフゲーム」を作成する授業です。
目的のシミュレーションを実現させるためのルールを設定する力と、それを実現するプログラミングスキルが身につきます。ライフゲームの作成後は、プログラムの出力の確認や修正、改善を行います。
地域データを分析して地域課題を解決しよう

「 地域データを分析して地域課題を解決しよう」では、政府統計の総合窓口であるe-Statや、SSDSE(教育用のデータ分析汎用素材)、RESAS(地域経済分析システム)などから地域のデータを把握・分析して、地域が抱える課題について考えます。
統計データをグラフ化するスキルやデータから導き出される課題の設定、課題解決方法の模索、他者への提案といった、統計データを活用するための一連のスキルが身につく授業です。
高校のプログラミング教育で身につくスキル

高校のプログラミング教育で身につくスキルは、下記のとおりです。
- 知能・技能
- 思考力・判断力・表現力
- 学びに向かう力・人間性
具体的にどのようなスキルを得られるのか、見ていきましょう。
知能・技能
高校のプログラミング教育では、情報・情報技術に関する正しい知識と、それを活用して課題を設定・解決する知能・技能を習得できます。
また情報に関する法律やマナー、個人の責任といった情報リテラシーに関する知識も身につきます。
思考力・判断力・表現力

高校のプログラミング教育では、情報過多の社会で、必要な情報をピックアップして適切に活用していく思考力・判断力・表現力が身につきます。
同時に、複数の情報を結びつけて新たな意味を見出したり、情報を科学的に分析したりする力も身につきます。
学びに向かう力・人間性
情報技術への理解を深め、活用法を知るなかで、法律や制度、マナーを守ることの大切さを知り、情報モラルを高められるのも、高校のプログラミング教育の特徴です。
また、情報科社会に自ら参画していく積極性も身につきます。
プログラミングを本格的に学べる高校は?【通学・通信制】

2022年以降、一般的な高校の授業でもプログラミング学習が行われますが、「ゲームを作る」といった本格的なプログラミングの授業は基本的にありません。
しかし高校のなかには、本格的にプログラミングを学べるコースなどを設けている学校もあります。
- 東京実業高等学校電気科【ゲームITコース】
- ヒューマンキャンパス高等学校【通学型通信制高校】
- N高等学校・S高等学校 通学プログラミングコース【通学】
- G学院
将来の仕事にも活かせる実践的なプログラミング授業が行われている学校を、4校紹介します。
東京実業高等学校電気科【ゲームITコース】
東京実業高等学校は、東京都大田区にある私立高校です。
電気科ゲームITコースでは、ゲームプログラムを通じてIT分野に関する知識を習得できます。理系大学進学を目標においた学習指導にも力を入れており、将来につながる学習を行えるでしょう。
3年間の集大成としてのオリジナルゲーム制作と「東京ゲームショウ」での発表・展示も行われます。
ITパスポート試験や基本情報技術者試験など、さまざまな関連資格の取得も可能です。
ヒューマンキャンパス高等学校【通学型通信制高校】
ヒューマンキャンパス高等学校は、全国に学習センターがある通信制の高校です。
数多くの専門コース課程を設けており、「プログラミング」「パソコンIT(情報処理)」「AI・ロボット」といったプログラミング関連のコースも充実しています。
プログラミングコースでは、現役のプロによる対面授業とオンライン授業を組み合わせた学習が行われます。基礎から実践まで一貫して学べるので、プログラミング知識やスキルに自信がない人でも安心です。
N高等学校・S高等学校 通学プログラミングコース【通学】
KADOKAWA・ドワンゴによる通信制高校が、「N高等学校」と「S高等学校」です。プログラミングを専門的に学びIT業界で活躍できる人材を目指します。
カリキュラムや学費など、基本的な部分はどちらの高校も同じです。通学先のキャンパスは全国に19カ所あり、通学プログラミングコースは、東京代々木と大阪梅田の2カ所です。
N高・S高共に通信制高校ですが、通学プログラミングコースでは週5日キャンパスに通って学習を行います。
G学院
G学院は、ゲームプログラミングに特化した学校です。現役プログラマーの講師が実践的なプログラミングを指導します。
ただし、G学院自体は高校ではありません。高校卒業資格を取るためには、別途提携の通信制高校への出願が必要です。なお通学は週3日で、高校卒業のための学習支援が行われています。
高校生が学校以外でプログラミングを学ぶには?

高校生がプログラミングを学べる場所は、学校だけではありません。授業を通して「もっとプログラミングを学びたい」と思ったら、積極的にチャレンジしてみましょう。
学校以外の学習方法には、次のようなものがあります。
- 本を読む
- プログラミングスクールに通う
- 資格取得を目指してみる
- 学生向けプログラミングコンテストに参加する
- ゲーム感覚でプログラミングが学べるサイトやアプリを活用する
プログラミング学習は、空き時間や勉強の息抜きに少しずつ進めることも可能です。短時間で見られる学習動画や無料アプリ、英語も勉強できる海外ゲームなどもありますから、チェックしてみてください。
優良プログラミング教育教材について、下記の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

ゲーム感覚で楽しく学べるプログラミングアプリはこちら
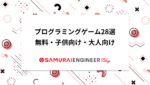
まとめ

高校生になると、大学受験や就職など、自分の未来について考える機会も多くなっていくでしょう。
高校のプログラミング教育では、高校卒業後どのような道に進んだとしても役立つスキルを学べます。主体性を持って取り組み、高校での学びを将来につなげていきましょう。
周囲の大人も、高校のプログラミング教育について確認し、進路の選択肢を広げるサポートすることが大切です。
この記事のおさらい
高校のプログラミング教育は、2022年度以降に入学した生徒から年次進行で必修化されます。
高校のプログラミング教育では、PythonやJavascriptのようなプログラミング言語を含む学習を行います。どの言語を学ぶのかは、それぞれの学校によって異なります。