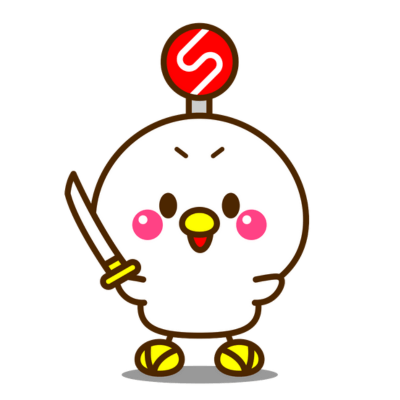プログラミング必修化とは

プログラミング必修化とは、文科省が学校での授業にプログラミング教育を必修化したことを指し示す言葉です。文科省がプログラミングを必修化したことで、豊かな人間性を育み将来の生活に役立つプログラミング技術を、小学生の段階から学べるようになりました。
2020年度に改訂される「学習指導要領」
文部科学省によると2020年度に改訂される「学習指導要領」にプログラミングの必修化があります。プログラミング教育を通して子供たちにIT技術者への道が開かれ、豊かな人間性と論理的思考ができる人材への育成が始まります。
プログラミング教育が小学校で必修化する理由
プログラミング教育を小学校で必修化することで、将来、生活や仕事に役立てることができるという目的があります。日本も含めて世界中が、IT無くして成り立たない時代といわれています。
IoT(Internet of Things)という、ものとものをインターネットでつなぐ時代が到来しています。子供たちの未来を考えたとき、小学生という早い段階からプログラミングを学ぶことが当然の流れとなっています。
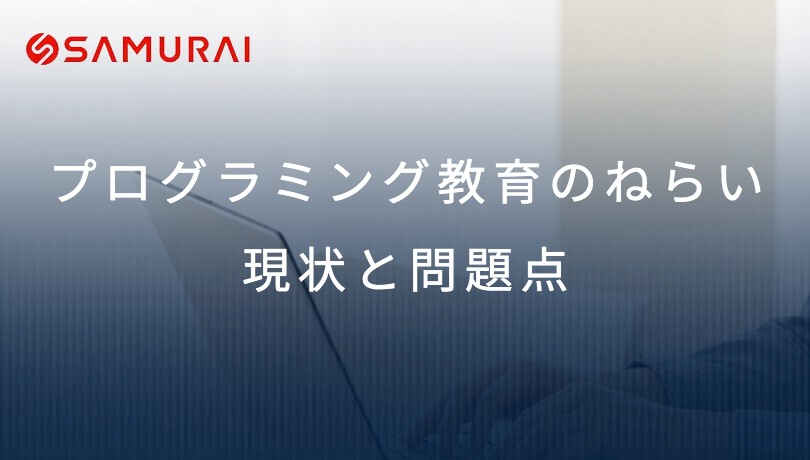
プログラミングを必修化する文科省の目的8選

プログラミングを必修化する文科省の目的を、8つ紹介していきます。
プログラミングを学校で必修化する時代が到来しました。文科省の狙いを正しく把握するために、プログラミングを必修化する必要がなぜあるのか、詳しく考察していきます。文科省の目的を明白にすることで、プログラミングの必修化の役割を正しく理解できるようになります。ぜひ、参考にしてみてください。
プログラミング的思考の育成
文科省がプログラミング学習を必修化したのは、プログラミング的思考の育成をするためです。プログラミング的思考とは、物事を理論立てて正しく解釈・説明できる能力のことです。
小学生の段階からプログラミング教育を受けることで、記号を使って物事を理路整然と理解・説明できる、論理的な思考ができる人間を育むことを文科省が推進しています。
順序立てて問題解決型の思考の育成
文科省がプログラミング教育を取り入れた目的のひとつに、順序立てた問題解決ができる思考の育成があります。順序立てた問題解決型の思考とはコンピュータの考え方です。
プログラミングとは、大きな問題を細分化した思考を組み合わせて解いていく学問です。このような考え方ができる人間を文科省は育成しようとしています。ひとつの問題に対してあらゆる角度から考えられることができる、細やかな思考の持ち主を目指しています。
プログラミング的思考は将来性が高い
文科省が目指しているプログラミング的思考能力を持つ人間は、将来性が高いといわれています。文科省が推進しているプログラミング必修化を実践することで、論理的な思考を兼ね備えた人材が育つと考えられています。
プログラミング的思考能力である論理的な人間が増えれば、社会の秩序が守られるでしょう。問題解決の際にも理路整然とした思考ができるため、正しい選択ができる可能性が高まるからです。
グローバル化に対応する人材を育てる
文科省がプログラミングを必修化する目的は、グローバル化に対応する人材を育てるとためです。プログラミングは世界共通の言語を学ぶのと一緒です。プログラミングができれば世界中の人間とつながることができます。
また、世界中で促進されているIT化に、文科省が推進しているプログラミングの必修化が役立ちます。将来、世界で役立つ人材を育成することが可能になるからです。
将来のIT人材の不足を補うため
文科省がプログラミングを必修化する目的は、将来のIT人材の不足を補うためという理由が大きいです。現在、IT化が進んでいる世の中ですが、日本は圧倒的に人材不足です。
そのため、文科省がプログラミングの必修化を積極的に進めています。
勉強や興味へのやる気を高める
文科省がプログラミングを必修化したのは、子供たちに勉強への興味とやる気を起こさせるためです。子供たちにプログラミングという新しい課題を与えることで、知的好奇心を刺激していくことを目的としているのが、文科省が必修化したコンピュータの授業です。
プログラミングという将来性のある教育を子供たちに必修化させることで、やる気を高めることができると期待されています。
PCを作動させるプログラミングの理解
文科省がプログラミングを必修化した目的は、PCを作動させるプログラミングの理解を深めてもらうためです。現代の子供たちは生まれたときからパソコンなどのIT機器に囲まれています。
ボタンひとつで作動するPCの、プログラミングという内容を早い段階で理解してもらおうという狙いが、文科省のプログラミング学習の必修化にあります。PCを深く知ることで、使いこなせる人材を育成することを目的としています。
プログラミング教育で育む資質・能力
文科省がプログラミングを必修化した目的は、プログラミング教育で資質・能力を育むことです。プログラミング教育を通して、子供たちの情緒を育成したり論理的な思考能力を開花させたりすることで、豊かな人間性と社会性を培っていこうという文科省の狙いがあります。
プログラミングという新たな刺激が、子供たちの中に眠っている才能を引き出し、未来の社会に役立つ人材を生み出すきっかけになると期待されています。
プログラミング必修化のカリキュラムと姿勢
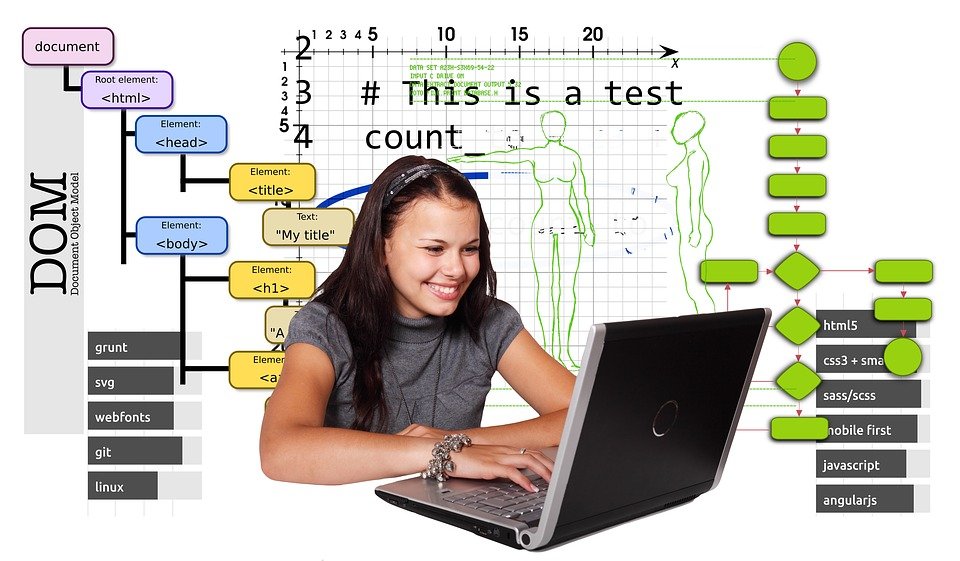
文科省のプログラミング必修化のカリキュラムと姿勢について紹介していきます。文科省がどうしてプログラミングを必修化したのかについて、その目的を理解したところで、今度は具体的な授業の内容について見ていきましょう。
ぜひ、参考にしてみてください。
各教科への組み入れ
文科省が推進するプログラミング教育必修化の、各教科への組み入れを見ていきましょう。内訳は、算数・理科・総合的な学習の3つの時間です。それぞれに学習の目的があり、プログラミングを通して深い洞察力や論理的思考を身につけることができます。
算数
算数は小学校5年生に必修化している正多角形を利用したプログラミングの授業です。正多角形を活用して、その意味を知ったり作図をしたりする内容です。プログラミング学習サイトScratchが使用されています。
学習の目的は作図ではなく、どのようなプログラミングを組んでコンピュータに命令をくだせば、自分が思い描いた図に近づくかを習得することです。
理科
理科のプログラミング教育の必修化には、「WeDo2.0」などのプログラミング教材が使用されています。電気を効率的に使うにはどうすればよいかというテーマでプログラミングを勉強します。
具体的にはコンピュータ内臓のブロックを組み合わせることで、モーターを動かす体験などをすることができます。スイッチロボットなどのセンサーの勉強を、電気を大切に使う教育とともに効率よく学べます。
総合的な学習の時間
文科省が推進するプログラマーの必修化の授業の総合的な学習の時間では、住んでいる地域の魅力を発見しながら、世間に発信するためのプログラミングを学習していきます。
探究心を育てると同時に、知り得た情報を的確にアウトプットするためのプログラミングの知識を学習していきます。情緒面もきたえられる画期的なカリキュラムです。
プログラミングの理解が成績に直接影響しない
文科省が推進するプログラミングの必修化は、プログラミングの理解が成績に直接影響しない点が特徴です。学校の成績に反映されることなく、子供たちに自由にプログラミングを学んでもらうことができます。
中学校や高校でも教育範囲などが拡充
文科省が推進するプログラミング教育の必修化が、今後は中学校や高校の教育に取り込まれていく予定です。小学校が先んじてプログラミング授業の必修化を始めましたが、次は中学校や高校へと教育範囲が拡充されていく予定です。
プログラミング必修化の目的は将来への前進

プログラミング必修化を通して、子供たちの将来への道が開けています。文科省の目的は、子供たちにプログラミングを効率よく習得してもらいながら、よりよい未来を作り上げていくことです。そのための必修化であることを常に意識しながら、プログラミングの授業を受けさせてあげてください。